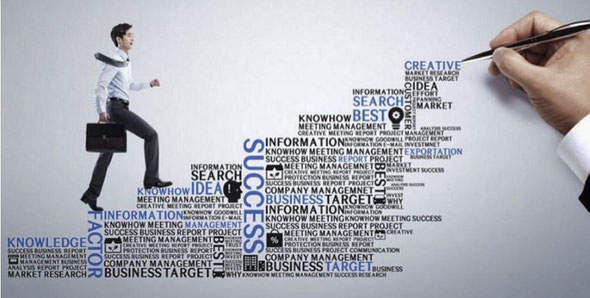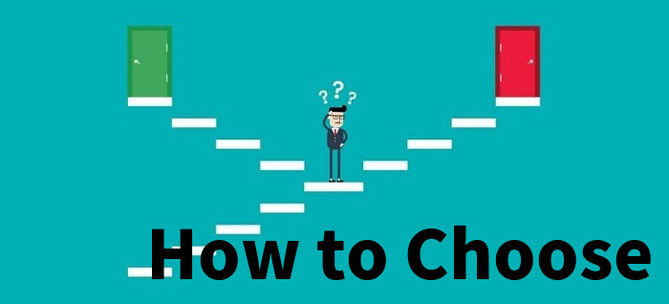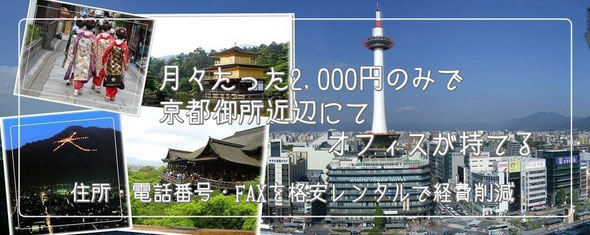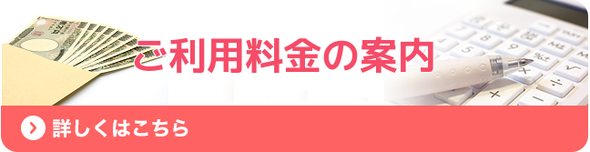起業するならバーチャルオフィスの活用がおすすめ!法人登記可能だかデメリットもあり
HOME > バーチャルオフィスとは? > 起業
「起業をしたいんだけど、バーチャルオフィスって使っても本当に大丈夫なの?」
「バーチャルオフィスで法人登記や銀行口座の開設はできるのかな」
「そもそもバーチャルオフィスとレンタルオフィスの違いはなに?」
起業をする際にバーチャルオフィスの利用を検討している方は、上記のように悩んでいるかもしれません。
詳しくは本文で解説しますが、バーチャルオフィスを活用した起業は十分に可能です。
法人登記や銀行口座の開設時にバーチャルオフィスを利用していても問題ないからです。
それに付け加えてバーチャルオフィスはレンタルオフィスに比べて費用が圧倒的に安くなっています。資金が何かと不足しがちな起業にこそ、バーチャルオフィスは特におすすめのサービスといえます。
しかしそうなりますと「話しがうますぎるな。バーチャルオフィスにデメリットはないの?」と疑問に思いますよね。
そこでこの記事では、起業時におけるバーチャルオフィスの基本情報だけでなく、活用事例・サービス内容・メリットやデメリット・費用・選び方などを解説します。
この記事を読めば、あなたが起業をする際にバーチャルオフィスを利用すべきかが一発でわかります。「起業時にバーチャルオフィスを活用すべきか、なかなか決められない……」と悩んでいる方は、ぜひ読んでみてください。
バーチャルオフィスでも起業・法人登記は可能
まずはバーチャルオフィスに関する基本情報を解説します。- バーチャルオフィスとは?
- バーチャルオフィスの活用事例
- バーチャルオフィスとレンタルオフィスの違い
バーチャルオフィスとは?
バーチャルオフィスは、直訳すると、「仮想の事務所」。言葉の通り、実在するオフィスではなく、住所や電話番号など事業運営に必要なオフィス機能だけ借りられるサービスです。詳しくは別章で解説しますが、バーチャルオフィスでも法人登記・銀行口座の開設は可能です。
ちなみに、なぜこのようなサービスがあるのかというと、「法人登記・銀行口座を開設するために住所が必要だな。でも自宅の住所は公表したくない」というニーズがあるためです。
そもそも起業時の手続き内容を調べてみるとわかるのですが、多くの提出書類にて法人の所在地を記載しなければなりません。その最たる例として登記申請書でいえば、以下の事項を記入します。
1.本 店 ○県○市○町○丁目○番○号 引用元:法務局|
(取締役会を設置しない株式会社の発起設立)(2023年4月9日時点)
登記申請書は、起業をする際に提出が必須の書類です。住所がなければ、この書類すら作成できないというわけです。この事実を踏まえますと、起業時には前もって法人所在地を用意しておかなければならないことがわかります。 しかしだからといって、起業のために自宅の住所を公表するのは抵抗がありますよね。
そんな悩みを解決するために、バーチャルオフィスというサービスが誕生したのです。 バーチャルオフィスを利用すれば実際のオフィスを借りる場合に比べて、自宅以外の住所を簡単に手に入れられます。
※バーチャルオフィスを借りる際も、一般オフィスやレンタルオフィスを利用するのと同じように一定の審査があります。 詳しくは後述しますが、費用が圧倒的に安いからです。下見に行く必要もありませんし、ネットから簡単に申し込めます。
バーチャルオフィスによっては、1~2週間ほどで利用できるようになるでしょう。このスピード感は、バーチャルオフィスならではの特徴です。 「起業のためとはいえ、自宅の住所は公開したくない」「オフィスをレンタルしたいが、時間はかけたくない」という方は、バーチャルオフィスをぜひ使ってみてください。
「おすすめバーチャルオフィスや格安サービスを比較したい方や電話番号の取得方法はこちら」
【最新版】おすすめバーチャルオフィス11選と住所利用最安値プランの紹介
【保存版】バーチャルオフィスにおいて電話番号を取得するメリット・注意点とは?
バーチャルオフィスの活用事例
バーチャルオフィスを活用して起業した事例はたくさんあります。例えば弊社のバーチャルオフィスを利用しているお客様でいえば、以下のような事例があります。
| 業種 | 利用開始時期 |
| 和装関連商品の問屋 | 2013年4月~ |
| ネットでの書籍・CD・DVDの販売 | 2013年5月~ |
| スペイン雑貨のネット販売 | 2013年10月~ |
| アプリ制作 | 2013年6月~ |
| ホームページ制作 | 2013年12月~ |
| WEBサービス運営 | 2016年8月~ |
| 写真・動画撮影サービス | 2015年7月~ |
| 求人広告代理店 | 2014年11月~ |
参考:京都バーチャルオフィス|お客様の声(2023年4月9日時点)
起業時はもちろんですが、上記のようにオンラインショップ・フリーランスの活動にバーチャルオフィスを用いるのもアリです。ぜひ一度ご相談ください。
バーチャルオフィスとレンタルオフィスの違い
バーチャルオフィスとレンタルオフィスの違いはいくつもありますが、まとめますと以下のとおりです| 異なる点 | バーチャルオフィス | レンタルオフィス |
| オフィススペース | 特になし※ | 完備 |
| 個室 | 特になし | ケースバイケース |
| オフィス設備 | 特になし | 完備 |
| 賃料 | 月々数千円 | 月々数万円 |
※完備しているバーチャルオフィスもあります。なお弊社のバーチャルオフィスであれば、コワーキングスペースも別住所にご用意しております。
バーチャルオフィスの場合だと、バーチャルオフィスにて働くことを想定していません。そのこともあり、基本的にオフィススペース・個室・設備は用意されていません。
そのためバーチャルオフィスは「とりあえず住所だけ欲しい」「法人登記・電話番号の取得・郵便物の転送など、必要最低限のサービスがあればいい」という方におすすめのサービスになっています。1人社長やパソコン1つで完結する事業を行っている方は、バーチャルオフィスをレンタルすれば十分でしょう。
その一方でレンタルオフィスは「一定の広さを有している部屋を利用したい!」と考えている方におすすめの形態です。そもそもレンタルオフィスとは、現実世界にて実在するオフィスを複数の個人もしくは法人がシェアして利用するサービス形態を指します。例えますと、とあるビルのフロアを複数の法人でシェアするイメージです。
レンタルオフィスであれば設備などを自分ですべて揃えなくとも、仕事ができる環境を瞬時に構築・従業員に提供できます。自宅で作業ができない方・一定数の従業員を抱えている方・設備関連の初期費用を抑えたい方には、レンタルオフィスがおすすめです。
バーチャルオフィスのサービス内容を解説
- 郵便受け取り・転送サービス
- 電話やFAXの取次サービス
- 電話番号の貸し出しサービス
- 会議室利用サービス
- 法人登記サービス
- 会計代行サービス
- 融資・補助金・助成金のサポート
- Webサイト制作のサポート
郵便受け取り・転送サービス
バーチャルオフィス宛に送付される郵便物を代わりに受け取り、指定した住所などに転送してくれるサービスです。住所貸しに注ぐ基本サービスと位置付けられています。転送サービスは、1通当たりの従量制が一般的。さらに、郵送物の中身がバーチャルオフィス宛に届いているかを通知してくれるサービスがあります。 ただし制限を超過した場合、料金が加算されるケースがあるので注意しましょう。電話やFAXの取次サービス
住所貸しと同時に運営会社からサービスで、住所にリンクした固定電話やスマートフォンに、電話やFAXを転送してくれるサービスです。 また、専門のオペレーター(電話秘書代行)が対応するサービスもあります。電話番号の貸し出しを含む取次サービスの基本料金に含まれるのが大半です。専用のオペレーターが対応するサービスは、1コール当たりでいくらという形で料金が生じます。電話番号の貸し出しサービス
「お持ちのスマホに専用アプリをダウンロードするだけで固定電話化する方法はこちら」
具体例を言いますと、弊社の電話番号貸し出しサービスをご利用頂ければ、京都の市街地局番である『075』番を取得可能です。 固定電話番号を取得することで、社会的信用は上がります。 例えば企業ホームページの連絡先に『090-○○○○-△△△△』と『075-☆☆☆☆-××××』 と記載されている場合だと、後者の方が安心できることでしょう。 前者だと「企業の連絡先なのに、携帯電話専用の番号である『090』番? この企業は本当に大丈夫なのかな。仕事を依頼しにくいな……」と心配されるかもしれません。
これでは本来獲得できた案件を逃すことになるハズ。 このように電話番号1つでビジネスに大きな影響を与えうるのです。この効果は、立ち上げたばかりの企業であり、認知度が低い企業ほど重要であるといえます。
会議室利用サービス
営業職などの事業者は、取引先と打ち合わせをする機会も多いでしょう。その際、運営会社から必要なスペースを借りられるサービスです。 バーチャルオフィスのビル内に用意されている会議室を事前予約することで利用が可能。料金は、1回当たりの利用で加算されます。法人登記サービス
基本サービスの住所貸しに付随して、法人の登記や登録ができるサービスです。法人登記は、会社に必要な情報を法務局に登録し、公表できるようにすることですが、バーチャルオフィスでも法人登録はできます。 登記場所として記載する住所は、実体がないバーチャルオフィスなどでも違反・違法ではありません。「バーチャルオフィスで法人登記する方法や注意点はこちら」
バーチャルオフィスで法人登記できる?メリットや法人口座が作れるか等も解説
バーチャルオフィスは違法?利用できない業種や注意点を紹介します
会計代行サービス
会社設立の際に必要な書類の作成や、記帳などの経理業務を、バーチャルオフィスと提携する司法書士や税理士に委託できるサービスです。 会社設立時だけでなく、領収書や通帳コピーなどを基に、会計帳簿や計算書類も作成します。
「オンラインで秘書業務を丸投げしたい方はこちら」
融資・補助金・助成金のサポート
バーチャルオフィスによっては、融資・補助金・助成金のサポートを行っています。提供サービスの内容にもよりますが、基本的には以下3つのサービスの利用が可能です。
| サービス内容 | 詳細 |
| 融資プランの提案 | 企業の規模や業種に沿ってプランを作成 |
| 書類作成の支援 | 融資申請時に必要な書類の作成を支援 |
| 補助金・助成金情報の提供 | 利用できる補助金などの案内 |
融資プランの提案では、企業の業種や規模に応じた最適なプランを選定し、資金調達の成功率の向上を期待できます。「今のままだと自己資金が〇カ月後には尽きそうだから、どうしても融資を成功させなければ……」と考えているのであれば、利用すべきです。
書類作成の支援では、事業計画書や収支計画書など、融資申請に必要な書類の作成をサポートし、手続きをスムーズに進めることができます。これまでのキャリアでこのような計画書作成したことがない方は、利用したいところ。
また、補助金・助成金情報の提供では、適切な制度を活用することで、企業の負担を軽減し、事業拡大につながります。補助金や助成金の有無・内容・金額・条件は毎年コロコロと変わりやすいので、精通した人からアドバイスをもらえるのはありがたいことでしょう。 そもそも起業したばかりの頃だと、資金が限られているケースがほとんどのハズ。そのため銀行や信用金庫などからの融資を考える起業家の方は多いことでしょう。
しかし「融資を受けるためにはどうすればいいんだろう?」と悩むことも多いハズ。融資関連の学びの場など、そうそうないからです。 そんなときこそ融資・補助金・助成金のサポートを利用してみてください。
何を・どの手順で・どうすればいいのかを、丁寧に指導してもらえます。飲食企業など、初期費用がかさみがちな企業ほど、融資・補助金・助成金のサポートを使ってみてくださいね。
※弊社は2023年4月の時点では、融資・補助金・助成金のサポートを行っておりません。
Webサイト制作のサポート
バーチャルオフィスにもよりますが、Webサイト制作のサポートをしてもらえます。なぜこのようなサービスがあるのかと言いますと、法人口座を開設する際に以下のように企業サイトURLを求められることがあるからです。銀行口座開設の際に必要なもの:ホームページなど
ホームページのみでの審査も可能です
※当社チェック項目を満たすホームページに限ります引用元:GMOあおぞらネット銀行|事業内容確認書類について(2023年4月8日時点)
そもそも起業をするということは、売上や利益を入れるための法人口座が必要ですよね。そして法人口座を開設する際には、Webサイトがチェックされる。つまり起業時にはWebサイトがあった方が都合は良いという理屈になります。
もちろん、企業ホームページの開設は法人口座の開設に役立つだけではありません。SNSやYouTubeなどと併用することで、効率的なオンライン集客が可能となります。Web広告も活用すれば、さらに捗ることでしょう。 このように法人にとってWebサイトは、多方面から見て必要な存在になっています。
そのこともあり、バーチャルオフィスにてWebサイトの制作サポートを行っていることもあるのです。 「起業をするから会社のWebサイトを作りたいけど、どうすればいいのかな?」と悩んでいる方は、利用してみると良いでしょう。
※弊社は2023年4月の時点では、Webサイト制作のサポートを行っておりません。
バーチャルオフィスを利用して起業する8つのメリット
- 起業時の費用が大幅に削減
- 備品補充や清掃などといったコストが発生しない
- 都会の一等地エリアを住所に設定できる
- スムーズに利用開始できる
- プライバシーを保護できる
- 豊富なサービスを利用できる
- 銀行口座の開設が可能である
- 社会保険や雇用保険の申請に使える
起業時の費用が大幅に削減
バーチャルオフィスは、賃貸オフィスやレンタルオフィスを借りる時に比べ、費用が削減できます。特に、費用削減効果を発揮するのは、起業時とされています。バーチャルオフィスは、申し込んだ即日に利用の開始が可能です。 契約時の敷金・礼金がなく、インターネット通信回線の整備費用のほか、OA機器のリース、メンテナンス費用など設備維持費用、オフィス家具にかかる費用などはかかりません。
さらに、毎月のオフィスの家賃や、電気代やガス代などの光熱費もなく、通常の賃貸オフィスでは毎月10万円は発生すると見込まれるランニングコストがほぼゼロになります。
いかなる業態、業種であっても起業時は多額の費用がかかるというイメージがありますが、費用面の悩みは、バーチャルオフィスの利用によって、一気に解決できます。
「格安のバーチャルオフィスはこちら」
備品補充や清掃などといったコストが発生しない
起業をする際にバーチャルオフィスを利用すると、備品補充や清掃などといったコストが発生しません。当たり前の話なのですがバーチャルオフィスは物理的なものではないため、備品の消費や汚れの発生などといった事象が起こらないからです。そもそもオフィスを構えると、多くの場合で来客がありますよね。そのためオフィスは常に清潔で、備品に不備がないように整えておかなければなりません。それらが原因で来客に不便な思いをさせると、商談に悪影響があるかもしれないからです。
しかしバーチャルオフィスであれば、このようなことはありません。商談であればビデオミーティングで済ませればよいだけです。Zoomなどを利用するのであれば、背景画像をセットすれば必要以上の清掃をする必要はありません。もちろん、備品を逐一用意する必要もないでしょう。 その結果、清掃や備品補充などといったコストが発生しないわけです。浮いた費用はマーケティングや商品開発に充てるとよいでしょう。
都会の一等地エリアを住所に設定できる
バーチャルオフィスは、東京都心部など、都会の一等地に住所を設定し、信用力やブランド力を獲得できるメリットがあります。名刺やホームページに一等地の住所をビジネス拠点として記載できれば、取引先からの信頼を得やすくなったり、新規顧客を獲得できたり、ビジネス拡大のチャンスが広がる可能性があります。安いコストで錯覚資産を獲得したい個人事業主やベンチャー企業に便利なサービスです。「バーチャルオフィスで一等地に住所を書きたい方や個人事業主が利用するメリットはこちら」
バーチャルオフィスを利用して名刺やパンフレットに一等地の住所を書こう!
バーチャルオフィスを個人事業主が利用する目的やメリットを解説!
スムーズに利用開始できる
バーチャルオフィスは、賃貸オフィスやレンタルオフィスなどと比較した時に、内見が不要だったり、審査・契約が簡単だったりと手間がかかりません。 ネットで契約が完結するためスムーズに利用開始できるのも大きなメリットです。プライバシーを保護できる
個人で起業する場合、事業が軌道に乗るまで、自宅やカフェを利用して仕事をされる方が多くいます。 しかし、法人登記の際に自宅を登録すると、個人情報を公に晒すことになります。 バーチャルオフィスであれば、コストのかかる賃貸で事務所を借りることなく、住所のみを取得できるため、個人情報を晒す必要もありません。 プライバシーを守りつつ、コストも抑えたいという新規事業者におすすめです。豊富なサービスを利用できる
バーチャルオフィスは、郵便転送や電話代行に加え、会議室やセミナールームといった共用スペースのレンタルサービスも利用できるケースが多いです。 さらには、法人登記代行や経理代行などのサービスもあり、自宅にいながら面倒な事務作業のサポートを受けられる点が、はじめて起業される方におすすめです。銀行口座の開設が可能である
バーチャルオフィスを用いて起業しても、銀行口座の開設は可能です。以下のように『バーチャルオフィスでも口座開設可能』と明言している銀行もあるからです。登記されている法人所在地がバーチャルオフィス(レンタルオフィス)であっても口座開設いただけます。 バーチャルオフィスにて郵便物を受取・保管し、バーチャルオフィスより郵便物を転送するサービスをご利用の場合も口座開設いただけます。引用元:GMOあおぞらネット銀行|
したがって「バーチャルオフィスだと、銀行口座は開設できないのかな?」と心配になっている方も、安心してバーチャルオフィスを利用してくださいね。 ただし、法人口座の開設後に郵送される簡易書留を受け取らなかった場合は、口座を利用できないおそれがあります。
この簡易書留は、記入された住所が本当に実在しているかを確認するため、必ず行われる重要な措置となっています。絶対に受け取ってくださいね。
ちなみに銀行口座開設の留意点として、2008年に犯罪収益移転防止法が改正されて以降、銀行口座開設時の審査が厳格化されたことだけは覚えておいてください。 審査厳格化には、バーチャルオフィスが資金洗浄(マネーロンダリング)などの犯罪目的に使われたという背景があります。 このことから現在では、審査において契約者が本人であるかどうか、事業に実体があるかどうかを運営業者から厳しくチェックされます。
ただ、審査が厳しいほど運営業者が信用できる証拠です。銀行口座が開設できれば、その後の融資獲得などにも有利に働くので、しっかり見極めましょう。
「バーチャルオフィスでも銀行口座を開設したい方はこちら」
バーチャルオフィスで銀行口座を開設するにはどうすれば良いのか?審査のポイントを含めて解説
社会保険や雇用保険の申請に使える
バーチャルオフィスは、社会保険や雇用保険の申請に使えます。そう言いますのもバーチャルオフィス云々という話ではなく、日本の法律で企業は必要に応じて社会保険・雇用保険の加入が義務付けられているからです。 まず社会保険に関しましては、厚生労働省が以下のように公表しています。
○次の事業所は、厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務づけられています。
(強制適用事業所)
すべての法人事業所(被保険者1人以上) 個人事業所(常時従業員を5人以上雇用している)
引用元:厚生労働省|社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?
(2023年4月9日時点)
厚生年金と健康保険とは、社会保険のこと。つまり社会保険に加入することは企業の義務であり、政府から強制されていることを意味します。 『バーチャルオフィスは社会保険の申請に使える』どころか、『そういう問題ではなく、むしろ申請しなければいけない』ことがよくわかりますよね。
しかし個人事業所に関しては、『常時従業員を5人以上雇用している』ことが条件となっています。ご注意ください。 ただいずれにせよ社会保険はバーチャルオフィス・レンタルオフィス・自前のオフィスなど、オフィスの形態によって左右される制度ではないことを覚えておきましょう。 次に雇用保険ですが、こちらに関しましても以下のように明記されています。
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
引用元:ハローワークインターネットサービス|雇用保険制度の概要
(2023年4月9日時点)
『強制』という言葉が使われていますよね。政府の管轄サイトでこのような強い言葉が使われているのが印象的なのですが、 それぐらい雇用保険は加入しなければいけない制度であることが伺えます。したがって社会保険・雇用保険の加入を重視している方も、安心してバーチャルオフィスを利用してください。
ただ、留意点があり、社会保険や雇用保険に申請する時、資金台帳など必要書類がしっかり確保されている状態か、各種保険の管轄窓口で確認されることがあります。 資金台帳など必要書類は保管義務があるためです。
「バーチャルオフィスでの起業後、社会保険加入の注意点を知りたい方はこちら」
バーチャルオフィスでの起業後に社会保険に加入する際の注意点とは?
バーチャルオフィスを利用する際のデメリット
- 開業できない業種もある
- 住所が他の利用者と重複する
- 郵便物の受け取りが遅くなる
- 突然の来客に対応するのが難しい
- 銀行から融資を受ける際に不利かもしれない
- 同一住所に同じ名称の企業は登記できない
- オフィスが閉鎖されるかもしれない
- 働く場所を別に用意しなければならない
開業できない業種もある
事業内容により許認可が必要な業種の場合は、バーチャルオフィスでは開業が制限されている業種もあるため、注意が必要です。 具体的には、職業紹介業や人材派遣業、建設業、不動産業などです。
いずれの業種も、行政の許可や管轄の警察署への届け出が求められるほか、確保する事務所の専用スペースや面談用スペースを確保しない限り、開業ができない要件が定められています。 事務所として営業をしているという実態が確認されないと、監督省庁から違反とみなされるケースが多いです。
「バーチャルオフィスと許認可の取得について知りたい方はこちら」
住所が他の利用者と重複する
バーチャルオフィスは、会社や事業者として使う住所が他の利用者と重複してしまうことがあります。 住所の重複は、バーチャルオフィスの運営会社が提供できる住所に限りがあるからです。 昨今は、バーチャルオフィスの利用者が増えており、住所が重複するケースも増えています。事前に運営会社に確認を取ったり、インターネットで調べたりするなどし、事前に重複を防ぐ対策を取りましょう。「京都のバーチャルオフィスをお探しの方はこちら」
郵便物の受け取りが遅くなる
バーチャルオフィスを使って起業をすると、郵便物の受け取りが確実に遅くなります。バーチャルオフィスの所在地に届いてから、あなた宛てに転送をされるからです。 例えばあなたの所在地が北海道で、バーチャルオフィスの所在地が京都だとします。すると日本年金機構や銀行などから書類が発送された場合、まずは京都のバーチャルオフィスに郵送されます。
そして、その後に北海道へ郵送されます。そのため、この郵便物の受け取りは、通常に比べて1~2日は遅くなることでしょう。 「1~2日ぐらいの遅れであれば、大した問題じゃないな」と感じるかもしれませんが、問題はここからです。
実はバーチャルオフィスにはオプションで転送設定というものがあります。これは『郵便物を毎日転送するか・定期的に郵送するか』を選べるシステムです。 転送設定を『毎日』にしているのであれば、郵便物の受け取りは1~2日ほどの遅れで済みます。しかし定期、例えますと1週間ごとなのであれば最大で7~8日ほど受け取りが遅くなるかもしれないのです。
起業したての頃は、銀行から法人用クレジットカードが入った簡易書留など重要書類が届くことがあります。そのこともあり、最初は基本的に毎日転送する設定にしておくのがおすすめです。 ただし転送設定にて毎日を選んだ場合は、1,000円前後のオプション費用がかかります。ご注意ください。
*弊社「京都バ―チャルオフィス」の場合、近隣に住んでいる方は直接引き取りに来ることも可能です
突然の来客に対応するのが難しい
バーチャルオフィスを利用して起業をすると、突然の来客に対応するのが難しいです。バーチャルオフィスにもよりますが、 来客対応をする際に必要となる打ち合わせ会議スペースのレンタルは事前予約が必要なケースがあるからです。そのため日時にもよりますが、突然の来客対応は困難になることがあります。 それに付け加えてバーチャルオフィスの利用者の中には、バーチャルオフィス周辺に住んでいないケースもあります。 想像してみてほしいのですが、京都のバーチャルオフィスを借りており北海道に住んでいて現在あなたは北海道にいます。 そんなとき、「今オフィスの前にいるんだけど、会える?」と言われても、対応はほぼ不可能ですよね。
仮に会議スペースを確保できたとしても、あなたがその場にすぐ駆け付けるのは難しいでしょう。 このようなケースではオンラインミーティングにて面談を実施するか、日を改めて再訪して頂くかが、現実的な対応策になります。
銀行から融資を受ける際に不利かもしれない
バーチャルオフィスを活用した起業だと、銀行から融資を受ける際に不利かもしれません。実体のないオフィスをレンタルしていることが、融資におけるプラス評価になることは考えにくいからです。
そもそも銀行から融資を受ける際は、以下のような条件が設定されています。
ご利用いただける方は、例えば以下の条件を満たす法人のお客さまです。
【1】業歴2年以上であること
【2】三井住友銀行のお取り扱い窓口(エリア・法人営業部・支店)でお取引が可能な地域に所在すること
【3】最新決算期において、債務超過でないこと
※債務超過とは、貸借対照表の純資産の部がマイナスであること
【4】お申し込みの時点において、税金の未納がないこと
※一部の窓口ではお取り扱いできません。
※お手続に際しては、エリア・法人営業部・支店まで、ご来店いただくことになります。
※地域によっては、お取り扱いできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
引用元:三井住友銀行|資金の調達 中小企業向け融資ビジネスセレクトローン
(2023年月4日時点)
簡単にまとめますと『返済能力があること』が融資における1つの条件といえます。 そして本題はここからで、通常のオフィスであれば賃料として1か月に数十万円支払うことになりますよね。これは一見するとデメリットに見えますが、裏を返せば毎月それだけの金額を支払えるだけのキャッシュがあることを示しています。
そのため現実世界にてオフィスを所有することで、「返済能力はある程度ありそうだな」と判断してもらえ、融資においてプラスに働くことが推測できます。社会的な信用を得やすいというわけですね。
しかしその一方でバーチャルオフィスのレンタル費用は非常に安いですよね。資本金が少なくても借りられます。 つまりバーチャルオフィスのレンタルでは現実世界のオフィスほど、「一定レベルの返済能力がありますよ!」とPRできないという理屈になるのです。
そのこともあり、「この企業はバーチャルオフィスを借りているのか。資金力は大丈夫なのかな。倒産なんてしないよね?」と心配されるかもしれません。その結果、融資を受けられないおそれが出てくるのです。 融資の成功確率を少しでも上昇させたいのであれば、事業計画書などをしっかりと準備してくださいね。
同一住所に同じ名称の企業は登記できない
これはバーチャルオフィスに限った話ではありませんが、起業をする際、同一住所に同じ名称の企業は登記できません。以下のように法律が定められているからです。既存の他の会社と商号及び本店の所在場所を同一とする内容の設立の登記は、することができません(商業登記法第27条)。
例えば、「ホウム株式会社」と「ホウム合資会社」、あるいは「ホウム株式会社」と「株式会社ホウム」は、同一の商号には当たりませんので、上記の制限は受けません。
引用元:法務省|商業・法人登記 Q&A(2023年4月8日時点)
オフィスが閉鎖されるかもしれない
バーチャルオフィスをレンタルした場合、オフィスが閉鎖するおそれがあります。オフィスを経営しているのも、あなたと同じ一般企業だからです。 そもそもビジネスにおいて経営難や倒産はつきもの。2022年だけでも、以下のように数千もの企業が倒産しています。2022年(1-12月)の全国企業倒産(負債総額1,000万円以上)は、件数が6,428件(前年比6.6%増)、負債総額は前年比2倍増の2兆3,314億4,300万円(同102.6%増)だった。 件数は、2019年(8,383件)以来、3年ぶりに前年を上回った。ただ、2年連続の6,000件台にとどまった。
引用元:東京商工リサーチ|全国企業倒産状況(2023年4月8日時点)
そのためどこのバーチャルオフィスを借りたとしても、運営元が倒産し閉鎖されるおそれは少なからずあります。 肝心の対策方法なのですが、バーチャルオフィスを借りるときは運営元企業の資本金などといった経営体力を事前に確認しましょう。
経営体力が非常に高い企業が運営をしていれば、閉鎖する確率は低くなるといえます。 また、万が一閉鎖をしたときに備えて契約書の内容を確認してください。サービス終了時の保証・手続きが明確に記載されていれば、安心して契約できます。
肝心の対策方法なのですが、バーチャルオフィスを借りるときは運営元企業の資本金などといった経営体力を事前に確認しましょう。経営体力が非常に高い企業が運営をしていれば、閉鎖する確率は低くなるといえます。 また、万が一閉鎖をしたときに備えて契約書の内容を確認してください。サービス終了時の保証・手続きが明確に記載されていれば、安心して契約できます。
働く場所を別に用意しなければならない
バーチャルオフィスを活用して起業した際、働く場所を別に用意しなければなりません。バーチャルオフィスにもよりますが、働く場所を提供していないことがあるからです。 もともとバーチャルオフィスは住所・電話・郵便物転送サービスの提供が基本。バーチャルオフィスをレンタルする人はそれを目的としており、以下のように自宅を作業場にすることがあります。ビジネスのアイデアはあったのですが、儲かるまでは事務所はいらなかったので、とりあえずは自宅でスタートしました。自宅やカフェなどでパソコンで仕事してますが、固定電話からの転送で会社っぽくなり助かってます。引用元:京都バーチャルオフィス|お客様の声(2023年4月8日時点)
このような事情もあり、バーチャルオフィスではコワーキングスペースを提供していないことがあるのです。バーチャルオフィスを借りたら、働ける場所を別に確保してくださいね。 ちなみに弊社のバーチャルオフィスであれば、コワーキングスペースも提供しています。もしも「ときどきはオフィスで仕事したい!」と考えているのであれば、弊社のバーチャルオフィスをご利用ください。
バーチャルオフィスを活用した起業が向いている人
バーチャルオフィスのメリット・デメリットがわかったところで、ここではバーチャルオフィスを使って起業をするのが向いている方を解説します。
- できるだけコストを抑えたい方
- 来客対応はできるだけしたくない
- プライバシーを守りたい
- 緊急の郵便物などがない
- 自宅やクライアント先で作業することが多い方
- 自宅で登記することが不可能な方
- 都市中心部での住所が欲しい方
- 社員が自分だけである方
できるだけコストを抑えたい方
バーチャルオフィスの強みはまず月額費用の安さです。 レンタルオフィスの賃料相場が2万円~なのに対して、バーチャルオフィスの相場は月額2000円〜と、コストを大幅に削減できます。 起業したばかりで固定費を抑えたい場合に向いています。
来客対応はできるだけしたくない
バーチャルオフィスは契約や申請をしない限り、会議室は使えません。
通常のオフィスであれば、来客があった時のためにお茶やお菓子を用意したり、レイアウトを気にしなければなりません。 バーチャルオフィスは消耗品やインテリアに費用を割くことはありません。
また、バーチャルオフィスの会議室はすぐに予約できるわけではありません。急な来社があった時には、近くの飲食店で対応してもよいでしょう。
プライバシーを守りたい
自宅で登記をする際に、住所や電話番号などの個人情報を公開することになります。プライバシーを守りたいなら、バーチャルオフィスを利用するとよいでしょう。 特に女性のニーズが高いようです。
緊急の郵便物などがない
バーチャルオフィスは、郵便物の転送サービスを備えていることがほとんどです。しかし、転送の頻度はさまざまで月に1、2回などの場合があるため確認が必要です。
状況に応じて、郵便物を取りに行かなければならないこともあるため注意しましょう。郵便物が多かったり緊急性の高い業種は不向きかもしれません。
自宅やクライアント先で作業することが多い方
自宅やクライアント先での作業が多い場合は、固定のオフィスである必要はなく、プライバシー保護の観点からもバーチャルオフィスが向いています。
自宅で登記することが不可能な方
自宅がマンションである場合、規約により登記することが不可能なことがあります。 自宅が登記できない場合、バーチャルオフィスを利用して登記することが手軽で最適といえます。
都市中心部での住所が欲しい方
起業の初期段階においては、取引実績もないため、どこに会社があるかといった細かい情報も重要です。 あまり聞かない土地に会社があるより、都心中心部の住所を利用するのがよいでしょう。
バーチャルオフィスは主に都市中心部にあるため初期段階のブランディングにも向いています。
社員が自分だけである方
バーチャルオフィスを活用した起業は、社員が自分だけの方に向いています。 1人だけであれば、必要以上に広いオフィスを構える必要がないからです。事業内容にもよりますが、例えばパソコン1つで成立するビジネスをしているのであれば、以下があれば十分でしょう。
- 広さ4畳ほどの部屋
- パソコン
- 机
- イス
なお作業場を自宅にするということは、自宅程度の設備・スペースがあれば仕事ができるということ。つまりオフィスや公園で仕事するなど、自由なワークススタイルの構築も可能です。 「当分の間、社員は自分1人だけだし自由に働きたいな」と考えている方も、バーチャルオフィスを借りてみてくださいね。
起業家必見!バーチャルオフィスの費用
ここではバーチャルオフィスの料金を解説します。弊社はバーチャルオフィスを提供しているのですが、以下のような料金体系になっています。| プラン名 | 料金/月額 | 主なサービス |
|
無料0円プラン
※利用条件あり |
|
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便の受取と転送月1回 ・ポストへ社名表示あり |
| エコノミー |
|
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便の受取と転送なし ・ポストへ社名表示なし |
| スタンダード |
|
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の受取・転送 |
| ビジネス |
|
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の受取・転送 ・電話番号取得・転送 ・スマホから市外局番通知可能 |
| プラチナ |
|
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の受取・転送 ・電話番号取得・転送 ・スマホから市外局番通知可能 ・FAX利用・転送 ・商談スペース (月10時間まで無料) ・郵便到着と転送をメールで通知 ・フリーダイヤル利用 |
引用元:京都バーチャルオフィス|月額基本料金無料!0円プラン
(2023年4月8日時点)
※1:無料プランは500円/1回の郵便物転送料金が発生します。
※上記は税抜き価格です。
※無料0円プラン以外では5,000円の入会金が初回に限り発生します。
資金が限られているのであれば、無料0円プラン・エコノミー・スタンダードのいずれかがおすすめです。
初期費用を抑えられつつ、一等地の住所を取得できます。「とりあえず住所だけでも取得しておきたい!」という方は、ぜひ利用してみてください。
その一方で資金に余裕があり「電話番号は必須だな」と考えているのであれば、ビジネスプラン・プラチナプランがおすすめ。
京都の市外局番を得ることで、顧客や取引先からの信頼を得られやすいでしょう。 またプラチナプランであれば商談スペースも利用できます。「取引をする際は、実際に顔を合わせて話をしたい!」と考えている方は、プラチナプランを利用してみてくださいね。
起業時におけるバーチャルオフィスの選び方
- 住所を確認
- サービス内容を確認
- 電話サービスの質を確認
- 犯罪歴などその住所にマイナスイメージがないかを確認
- 契約期間を確認
- 支払い方法を確認
- 駅からのアクセスを確認
- 外装や内装を確認
- スタッフが常駐かを確認
住所を確認
起業時にバーチャルオフィスを借りるのであれば、住所を必ず確認してください。上述しましたように、住所によっては社会的な信頼を得られるからです。
例えますと仮に同じビジネスをしている2つの企業、AとBがあったとします。Aの所在地は銀座であり、Bは田舎町だとしましょう。そうなりますと住所を起因とした安心感に違いが出てきますよね。
前者だと「賃料の高い銀座にオフィスを構えられるほど、利益が上がっているのかな? 大したもんだ」と思ってもらえる可能性があるからです。
すべての企業がこのように捉えるとは限りませんが、このようなことが考えられる以上、バーチャルオフィスを借りる際は住所を必ず確認してください。ビジネスを少しでも有利な環境で始められるようにしましょう。
なお、バーチャルオフィスの住所は基本的にTOPページに記載されていることが多いです。TOPページに見当たらない場合は、サイトマップから探してみてくださいね。
サービス内容を確認
起業時にバーチャルオフィスを借りる場合は、サービス内容を確認してください。選んだバーチャルオフィス・プランによっては、自分が望んでいるものを提供してもらえないかもしれないからです。
例えば先ほど弊社の料金体系を解説しましたが、プランによって内容が異なっていましたよね。無料プランだと、電話番号取得・転送を利用できませんでした。
そのため電話番号の取得を希望している方には、向いていないプランになっています。電話番号の取得を希望するのであれば、ビジネスもしくはプラチナを選択しなければなりません。
このことを理解していなければ、契約後に「利用できないの!?」と後悔するかもしれません。したがってバーチャルオフィスを借りる際は、サービス内容を必ず確認してくださいね。
電話サービスの質を確認
起業時にバーチャルオフィスを借りるのであれば、電話サービスの質を確認しましょう。一言で電話対応といっても以下のように3つのパターンがあるからです。- 人による電話応対
- 自分が登録した電話番号への転送
- 電話メッセージ
バーチャルオフィスにもよるのですが、人が必ず電話対応をしてくれるとは限らないわけです。基本的には『自分が登録した電話番号への転送』が基本となっています。
もしもあなたが「自分で電話対応はしたくない! けど人に対応してもらいたい!」と考えているのであればオペレーターが対応をしてくれるバーチャルオフィスを利用してくださいね。
犯罪歴などその住所にマイナスイメージがないかを確認
起業時にバーチャルオフィスをレンタルする際は、その住所に犯罪歴などのマイナスイメージがないかを必ず確認してください。借りた住所に犯罪歴などがあると、顧客もしくは取引先からの信頼を失うおそれがあるからです。
そもそもバーチャルオフィスには多くの法人が利用します。弊社のバーチャルオフィスでいえば、2023年4月時点で198もの事業者にご登録頂いています。
数百であればともかく数千・数万もの法人数にもなれば、そのバーチャルオフィスの所在地にて犯罪が発生する可能性は少なからず出てくるでしょう。
そして自分の借りているバーチャルオフィスの所在地に犯罪歴があった場合、顧客や取引先に知られてしまうかもしれません。今ではネット検索にて簡単に調べられるからです。
仮に自分には関係がなかったとしても住所が同じということで、あなたに疑いの目が向けられるかもしれません。この際に、その住所に複数の企業が入っていることに気づいてもらえないかもしれないからです。下手をしますと、取引だけでなく銀行口座の開設すら不利になるかもしれません。
このような事態を避けるためにも、その住所の犯罪歴などは、必ず確認してください。
契約期間を確認
起業時にバーチャルオフィスを借りるのであれば、契約期間を必ず確認しましょう。契約期間によって最終的なコストが変わるからです。
例えばとあるバーチャルオフィスを確認してみると、以下のようになっています。
プラン名 料金(税込)/月 年間プラン 5,170円 半年プラン 6,490円 単月プラン 8,140円
このように契約期間が異なることで、最終的に支払うコストが数万円単位で変わります。そのためバーチャルオフィスをレンタルする際は、必ず契約期間を確認してください。少しでもお得にバーチャルオフィスをレンタルしてくださいね。
支払い方法を確認
起業時にバーチャルオフィスをレンタルするのであれば、支払い方法を確認しましょう。当たり前の話なのですが、クレジット払いが可能である方が便利だからです。
万が一あなたの借りたバーチャルオフィスの支払いが『現金払いのみ可能』なのであれば毎月もしくは毎年、銀行またはATMに行く必要が出てきます。
起業したての頃は忙しいハズですから、このような時間はとてもではありませんがないでしょう。自分1人で経営・営業・マーケティング・会計など、すべてを行っている1人社長であればなおさらです。時間がもったいなさすぎます。
しかしクレジット払いが可能なのであれば、口座から自動で引き落とされます。支払うための移動時間などを確保する必要はまったくありません。「あっ、支払いに行かないといけないな」と思うことなく、常に業務に集中できます。集中できることで、業務効率も上がることでしょう。
以上のことから、バーチャルオフィスを借りる際は支払い方法を確認してくださいね。もしも支払い方法が公式サイトに記載されていないのであれば、問い合わせることを強くおすすめします。
駅からのアクセスを確認
起業時にバーチャルオフィスを借りるのであれば、駅からのアクセスを確認してください。クライアントとの打ち合わせに使う可能性があるからです。
もしもクライアントから「打ち合わせをしたいので、御社で打ち合わせをしたいのですが」と言われた場合、アクセスが悪いと不便ですよね。クライアントに煩わしい思いをさせてしまうかもしれません。
また場合によっては、気分転換を兼ねてバーチャルオフィスのコワーキングスペースを自分で借りることもあるでしょう。そんなとき駅からのアクセスが抜群であれば便利ですよね。移動に時間をかけなくて済みます。
先ほどもチラッと触れましたが、起業したばかりの頃はリソースが非常に限られています。資本力が乏しいことがほとんどでしょうから、人的リソースに関しては特に制限されているハズです。つまりあなたが業務を止めてしまうと、会社全体の業務もすべてストップするということ。
そのような状況下で、無駄な時間を過ごすのはどう考えても好ましくありません。あなたが無駄な時間を過ごしている間に、ライバル企業に差を付けられるかもしれないからです。時間は有限ですので効率良く、かつ有効活用しなければなりません。
そうなりますとバーチャルオフィスを借りるのであれば、やはりアクセスが良いかを確認すべきです。公式サイトにて所在地およびアクセスをよく確認してみてくださいね。
外装や内装を確認
起業時にバーチャルオフィスをレンタルするのであれば、外装や内装を確認してください。企業イメージに直結するかもしれないからです。
例えばあなたがバーチャルオフィスをレンタルしたとします。そして自社のホームページにバーチャルオフィスの所在地を記載しますよね。すると多くの場合で、顧客や取引先はその住所を調べるハズです。架空の住所を用いていないかを確かめるためです。
現在ではGoogle検索で、その住所を簡単に調べられます。問題はここからでGoogle検索で住所を検索すると、その住所に該当する建物が表示されます。そのときに、あまりにもボロボロなビルを利用していることが判明した場合、取引先はどのように思うでしょうか。
たいていの場合は「こんなところにオフィスを構えているのか。この企業、大丈夫?」と思われることでしょう。少なくとも、好印象を与えることはないハズです。
その一方で清潔で立派なビル(バーチャルオフィス)を借りていれば、話が変わってきます。「ずいぶん立派なオフィスだな。こんなところを借りているということは、ビジネスが上手くいっているんだろうな」と捉えられることでしょう。
このときの印象の差があなたに対する印象に直結し、ビジネスに影響を及ぼすことが考えられるのです。そうなりますと、どうせなら良い印象を得たいですよね。
したがってバーチャルオフィスを借りるのであれば、外装や内装をきちんと確かめておくべきなのです。さすがに現地に直接赴く必要はありませんが、Google検索などで確認ぐらいはすべきでしょう。10秒ほどで外装や内装をチェックできますよ。
スタッフが常駐かを確認
起業時にバーチャルオフィスをレンタルする際は、スタッフが常駐かを確認してください。緊急サポートを期待できるからです。
どういうことかと言いますと、例えば上述しましたがビジネスをしていると、クライアントがオフィスに訪れることがありますよね。クライアントによっては連絡なしで、いきなりオフィスに来ることも考えられます。そんなときでも常駐スタッフがいれば、丁寧な対応をしてくれることでしょう。迅速にあなたに連絡をしてくれるハズです。
しかしその一方で常駐スタッフがいない場合は、このような対応がまったくできません。クライアントからすれば訪問先に誰もいないわけですから、相当困惑するハズ。下手をしますと「誰もいない……。実在しない企業なのか!?」と疑われることでしょう。これでは今後のビジネスに悪影響を及ぼすことは必至です。
このような事態を回避するためにもバーチャルオフィスをレンタルするときは、常駐スタッフがいるかを確認してくださいね。自宅にて安心してビジネスを進めることができますよ。
バーチャルオフィスで起業した際によくある質問
ここでは起業時にバーチャルオフィスを利用した際、よくある質問を解説します。- バーチャルオフィスを利用している場合、納税地はどこになる?
- バーチャルオフィスの費用は経費で落ちますか?
- バーチャルオフィス以外のオフィス形態はどうなっていますか?
- バーチャルオフィスでも口座開設できるネットバンクはありますか?
- バーチャルオフィスを利用した起業手順はどうなっていますか?
- 起業に必要な書類はなんですか?
- バーチャルオフィスを利用した登記は違法ですか?
- 地方に移住してもバーチャルオフィスは使えますか?
バーチャルオフィスを利用している場合、納税地はどこになる?
◆個人事業主の場合
個人事業主は、事業の開始時に、開業届出書(個人事業の開廃業等届出書)を税務署に提出しますが、提出時に「納税地」「納税地以外の住所地・事業所」を記載する欄を自宅住所にするか、バーチャルオフィスの住所にするかで決まります。いずれの記入欄もバーチャルオフィスの住所、自宅住所のどちらの記入が可能です。税務署は、法人税や所得税といった国税を管轄しているので、納税地の欄に記載した住所に近い税務署に国税を支払うことになります。住民税などの地方税も同様です。開業届出書に記載した納税地に応じて、税金を納める都道府県・市区町村が決まります。◆法人の場合
法人は、税務署や県税事務所、役所に届け出る法人設立届出書の欄にある「その法人の本店または主たる事務所の所在地」(本店所在地)が納税地になります。つまり、法人税や所得税などの国税は、法人設立届出書で本店所在地に設定した住所のエリアを担当する税務署で納税することになるのです。一方、法人住民税などの地方税は、注意が必要です。法人住民税は、バーチャルオフィスの住所を本店所在地、自宅の住所を事務所所在地にそれぞれ設定した場合、2箇所に課税される可能性が生じます。つまり、納税額が増えてしまうかもしれないのです。ただ、バーチャルオフィスは名目上の住所で、基本的に業務は自宅ですると証明ができれば、法人住民税の徴収を1カ所にまとめられる可能性があります。事前に専門の税理士や公的機関に相談し、余分な納税を防ぎましょう。「バーチャルオフィスを利用した時の納税地について知りたい方はこちら」
バーチャルオフィスで起業・開業したときはどこに納税したらいいの?
バーチャルオフィスの費用は経費で落ちますか?
バーチャルオフィスの費用を経費として扱うのは、一般的には可能です。バーチャルオフィスは、仕事(特に登記など)に必要なモノであることが考えられるからです。多くの場合で、一般的なオフィスを借りているのと同じように経費で落とせることでしょう。ただし上記はあくまで一般論であり、起業ケースによっては異なるかもしれません。心配な場合は税理士に相談するとよいでしょう。
バーチャルオフィス以外のオフィス形態はどうなっていますか?
◆自宅
自宅は、主に個人事業主のビジネスに使われるオフィスで、自宅を仕事場と見立てて使います。
メリットは、もっぱら費用面。オフィスに移転する必要がないため、初期費用、ランニングコストを抑えられるだけでなく、自宅をオフィスとして利用するため、家賃や光熱費の一部を経費として計上が可能です。
メリットが多い印象ですが、仕事とプライベートのけじめが付きにくいほか、自宅住所を公表してしまうデメリットがあります。 このことから、子育てに励む女性や現役を引退した人に向いているオフィス形態と言えるでしょう。
◆レンタルオフィス
レンタルオフィスは、業務上必要な机やイス、インターネットが備わった賃貸事務所。利用すると、来客時の対応受付のほか、法人設立や各種会計業務などを代行してくれる運営会社もあります。
メリットは、費用と柔軟性。一般的な賃貸事務所と比べ、保証金などがなく初期費用が安いほか、運営会社によっては契約の延長や解約、期間設定に柔軟に対応してくれます。デメリットもあります。オプションサービスが充実しており、料金が高く付く場合があるほか、スペースの仕切り板が薄くプライバシーの問題が発生しがちなことです。 不特定多数が出入りするため、セキュリティ管理にも注意が求められます。これらの特徴から、レンタルオフィスは、個人の属性よりも、士業やWeb関連、コンサル業といった特定の業種に向いていると言えるでしょう。
「エリア別に京都のレンタルオフィスが知りたい方はこちら」
◆シェアオフィス
シェアオフィスは、異業種間の情報共有や人の繋がりを目的とした会社や個人が、共同で同じスペースに入居する新しい賃貸サービスです。主に、入居する他社から顧客獲得に必要な情報を入手したり、入居者から仕事を受注したりできるメリットがあります。一方、共同オフィスであることから、一般的な事務所と比べてプライバシーの面で大きいのがデメリットです。
こうした特徴があるシェアオフィスですが、クライアントを増やしたい起業直後の人や、異業種間でコミュニケーションを取りたい人が向いているとされています。
◆コワーキングスペース
コワーキングスペースは、従来の賃貸事務所と違い、共有のオープンスペースで仕事をするスタイルのオフィススペースです。
デスクや椅子、インターネットなど業務に必要な環境が揃っており、低コストで利用できたり、スペースを会議場所として使えたりするメリットがあります。他の共有型の共同オフィスと似ていますが、プライバシーに弱いのが難点。 シェアオフィスと異なり、共同ビジネスが創出しにくいのもデメリットです。こうした特徴を持つコワーキングスペースは、さまざまな職種やスキルがある人と交流を持ちたい人にとりわけ向いています。
「京都のコワーキングスペース紹介記事はこちら」
バーチャルオフィスでも口座開設できるネットバンクはありますか?
バーチャルオフィス業務を日々おこなっているとお客様が申し込まれた銀行口座開設関連書類が届きます。その中で最もよく見かけるのがGMOあおぞらネット銀行 です。弊社のお客様はスモールビジネスやインターネット関係が多いのですが、これらの方々から最も支持されていると言えます
【GMOあおぞらネット銀行の特徴とメリット】
・設立1年未満の法人であれば、他行宛の振込手数料20回/月無料
・他銀行の口座宛送金は、振込金額にかかわらず手数料一律145円(税込)
・オンライン完結で最短即日口座開設可能
・最大20口座まで追加で開設できるので用途ごとの使い分けができる
・24時間365日取引が可能なインターネットバンキング
・ビジネスデビット(銀行法人クレジットカード)も発行可能
バーチャルオフィスを利用した起業手順はどうなっていますか?
バーチャルオフィスを利用した際の起業手順としては、以下が考えられます。- 1.バーチャルオフィスを個人名で先にレンタル※
- 2.企業の概要を作成
- 3.印鑑を作成
- 4.定款を作成
- 5.資本金を払い込む
- 6.印鑑証明書・定款・設立登記申請書などを提出
- 7.法人設立
- 8.バーチャルオフィスの名義を法人に変更
- 9.Webサイトの開設
- 10. 銀行口座の開設
ポイントは、バーチャルオフィスを個人名義で先に借りておくということ。記事の冒頭でも触れましたが法人を設立する際、提出する書類に法人の所在地を記載しなければなりません。これは各書類を作成する時点で法人住所を持っていなければ、設立が不可能であることを意味します。
そういった事情もあり、法人設立前にバーチャルオフィスを先に借りておく(住所を用意しておく)必要があるのです。
その後無事に法人を設立できたら、法人設立が正式に済んだことをバーチャルオフィスに連絡します。これで自分の会社が、そのバーチャルオフィスを借りていることになります。 ちなみに定款などの作成に時間がかかりそうであれば、住所以外の部分を埋めてしまい、先に書類を作っておくというのもおすすめです。
そうすれば「書類の作成に手間取って、バーチャルオフィスのレンタル費用を無駄に2カ月分も支払ってしまった……」という展開を避けられます。状況に合わせて考えてみてくださいね。
起業に必要な書類はなんですか?
先ほどチラッと触れましたが、一般的な株式会社を設立・起業する際に必要な書類は以下のとおりです。- 定款
- 設立届
- 印鑑証明書
- 設立登記申請書
- 登記所在地変更届
- 資本金の払い込み証明書
- 登記簿謄本等記載事項証明書
バーチャルオフィスを利用した登記は違法ですか?
バーチャルオフィスを利用した登記は違法ではありません。もしも違法であれば、バーチャルオフィスという存在は今日まで続いていません。バーチャルオフィスを利用して起業をするという人も現れないでしょう。安心して利用してください。ただし記事の前半でも触れましたが、人材派遣業などオフィス要件が法律により指定されている業種がバーチャルオフィスを利用して起業するのは違法です。 ご注意ください。
地方に移住してもバーチャルオフィスは使えますか?
地方に移住してもバーチャルオフィスは利用できます。利用する際に所在地に基づいた規制は特にないからです。ネット環境さえ整っていれば、どこからでも申請・使うことができます。地方に在住しており「起業をしたいんだけど、事務所は京都に構えたいな」と考えている方は、ぜひ弊社のバーチャルオフィスをご利用ください。
まとめ|バーチャルオフィスを使っての起業は可能!
本記事では、バーチャルオフィスが提供するサービスをはじめ、メリット、見落としがちな注意点について解説してきました。 バーチャルオフィスは、コストを抑えてビジネスを円滑にしたいという事業者の味方です。最近は、ネットワーク環境が整っていることから、一念発起し自宅でビジネスを展開するフリーランサーが増えてきており、多額の初期コストをかける必要がないバーチャルオフィスは、今後もニーズが高まるサービスと言えるでしょう。
メリットと注意点の両方に留意し、賢く利用すれば、あらゆるビジネスシーンで役立つことは間違いありません。バーチャルオフィスサービスを活用して起業してみませんか。
バーチャルオフィスなら京都バーチャルオフィス
京都バーチャルオフィスの特徴
京都バーチャルオフィスの強みは以下のとおりです。
・サービス内容に応じて選べる4つのプラン
・京都御所から徒歩1分の好立地
・月額1,500円〜!エリア最安値に挑戦中
・電話番号取得・転送サービス付きでも月額6,500円〜
・商談スペースもあり
特に月額料金の安さには自信があります。もし低コストで開業したい、初期費用を抑えたいとお悩みなら、ぜひ弊社にご相談下さい。
【京都バーチャルオフィスを利用中のお客様の声】
実際に京都バーチャルオフィスをご利用いただいているお客様の声をご紹介します。以下のお客様は大阪からご利用頂いています。
【ご利用プラン】ビジネスプラン
“ビジネスのアイデアはあったのですが、儲かるまでは事務所はいらなかったので、とりあえずは自宅でスタートしました。自宅やカフェなどでパソコンで仕事してますが、固定電話からの転送で会社っぽくなり助かってます。( J.I様 男性)
「京都のバーチャルオフィスを利用して開業をしたいという方はこちら」
京都バーチャルオフィスのプラン内容
京都バーチャルオフィスでは、以下4つのプランをご用意しています。それぞれの料金とサービス内容は次のとおりです。
| プラン名 | 料金/月額 | 主なサービス |
|
無料0円プラン
※利用条件あり |
|
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便の受取と転送月1回 ・ポストへ社名表示あり |
| エコノミー |
|
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便の受取と転送なし ・ポストへ社名表示なし |
| スタンダード |
|
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の受取・転送 |
| ビジネス |
|
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の受取・転送 ・電話番号取得・転送 ・スマホから市外局番通知可能 |
| プラチナ |
|
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の受取・転送 ・電話番号取得・転送 ・スマホから市外局番通知可能 ・FAX利用・転送 ・商談スペース (月10時間まで無料) ・郵便到着と転送をメールで通知 ・フリーダイヤル利用 |
このように、プランごとに料金やサービス内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選び頂けます。どのプランが適切か悩んだ際は一度ご相談下さい。京都バーチャルオフィスでは、適切なプランをご提案し、皆様のビジネスをサポートいたします。

京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは?
京都バーチャルオフィス
お電話でもお気軽にお問い合わせください
電話番号 075-257-7746
あなたへオススメの関連記事
この記事を読んだ方には下記ページも読まれています

手軽に住所や電話番号を取得できるというサービスでとても便利な反面、逆に言えば不正や犯罪に利用されやすいという課題があるのがバーチャルオフィス。これを防ぐために利用前にはしっかりと審査があります。審査を通過するポイントなどを解説していきます。