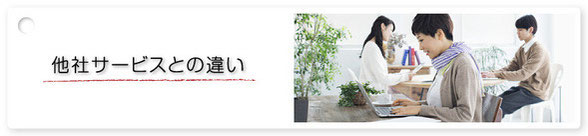バーチャルオフィスの契約はこんなに簡単!必要な書類と手順を徹底解説!失敗しないために知っておきたいポイントは?
HOME > バーチャルオフィスとは? > 契約
バーチャルオフィスは月額数千円で利用できることが大きな魅力です。しかし、契約までの流れや準備するべき書類が分からない方も多いのではないでしょうか?本記事は現在バーチャルオフィスを検討中の方を向けて、契約のフローや審査の注意点、用意するべき書類について解説します。
バーチャルオフィスの一般的な契約の流れ
バーチャルオフィスの使用開始までは、大きく4ステップに分けられます。それぞれのステップについて、以下で詳しく説明します。
【1】バーチャルオフィスの内覧予約を行う
まずは内覧予約を行いましょう。バーチャルオフィスを契約する前には実際に足を運び、オフィスの外観や実際のフロアを確認する必要があります。内観の流れは業者によりますが、主に受付や入居するフロア、会議室やラウンジなどを見て回ります。気になる点があった時はその場で即座に聞きましょう。内観は契約の判断をする重要なステップですので、見て回りながら次の点を確認しましょう。
・ビルの外観とオフィス全体の雰囲気
・会議室・商談スペースの広さ・清潔感
・写真と実際のオフィスに違いはないか
・担当者の説明に曖昧な点はないか
上記に関して少しでもおかしい・怪しいと感じた時は見送りをおすすめします。
【2】書類を提出する
内観して問題がなければ契約へと移ります。事前に用意しておいた書類を提出しましょう(必要書類については後述)。
バーチャルオフィスは犯罪収益移転防止法の対象で、本人確認や入居の審査などが厳格になっています。過去に悪用された経緯から必要書類も多いため、早めに準備を進めましょう。なお、書類は最短1日で集められますが、複数の公共機関へ出向くことになるため、数日かけて集めるとよいでしょう。
契約に必要な書類(弊社京都バーチャルオフィスの場合)
◆法人契約の方のみ◆
・履歴事項全部証明書 / 法人の印鑑証明書
◆個人事業主の方のみ◆
・住民票 / 個人の印鑑証明書
◆どちらも共通で必要な書類◆
・代表者免許証又は 顔写真入り身分証明書のコピー
・自宅公共料金の明細や請求書のコピー
希望転送先の住所、氏名いり
(電話、ガス、電気、水道、年金、健康保険など)
【3】入居審査
書類を提出した後は、犯罪目的で利用されることを防止するため所定の入居審査が実施されます。バーチャルオフィスの審査では、主に以下の点についてチェックが行われます。
・申込者の信用性の確認
・企業実態の確認
・業種のチェック
・事業内容や妥当性
業者によって審査項目が変わったり、追加書類の提出(会社案内パンフレットなど)を求められることがあります。もし追加書類を求められた時は応じましょう。審査結果は最短で即日判明しますが、通常は2~3営業日ほどかかるため、事前に聞いておくことをおすすめします。
【審査に落ちる可能性もある】
バーチャルオフィスの審査に落ちるケースは少なく、ほとんどの方は問題なく契約締結できます。しかし、審査に落ちる可能性もゼロではありません。特に次のようなケースは入居を断られやすいでしょう。
・事業計画書の内容や説明があいまい
・事業そのものに問題がある
・バーチャルオフィスで開業できない業種に該当した
これらに当てはまらないよう、慎重に準備を進めていきましょう。
【審査において最も重要なポイントは?】
「事業内容が客観的に確認できること」これに尽きます。最もシンプルに事業内容を確認してもらう方法としてはホームページやECサイトが存在していることです。しかしながら事業開始前でホームページが開設できていないこともありうるでしょう。こんなときはホームページが完成してからバーチャルオフィスへ申し込むことが確実です。もしあなたが急いでいてホームページが開設前にバーチャルオフィスと契約したいときは、それに替わる資料を提出しましょう
◆下記が一例になります◆
客観的に誰でも事業内容がわかる資料をご用意ください
主要取引先との契約書のコピーやフランチャイズ契約書のコピー、
各行政機関発行の許認可証、会社案内、製品、パンフレット
お取引先さま向けご提案書、見積書、注文書、仕様書等
【4】契約締結と入金
無事審査に合格したら契約書を交わし、指定期日までに料金を入金しましょう。入金を済ませれば、いよいよバーチャルオフィスを利用できます。ただし、契約書には解約条件など大切な事柄が書かれています。隅々まで読み、不明点やおかしいと感じた点があった際は担当者へ確認を取りましょう。
バーチャルオフィスの契約時に必要な本人確認書類は何?
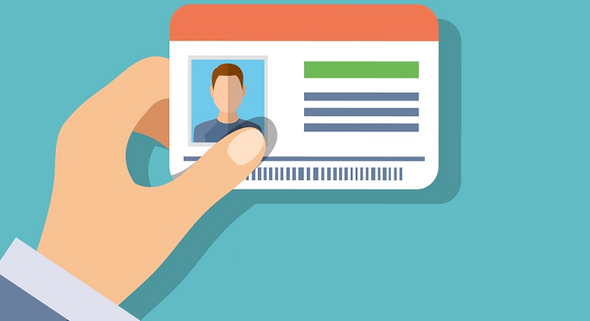
以上がバーチャルオフィス利用開始までの一般的な流れですが、契約にあたっては数種類の本人確認書類を提出を行う必要があります。しかし、個人で契約する場合と法人として契約する場合で提出書類が異なる点に注意しましょう。
個人事業主として契約する場合
まず個人で利用するケースですが、以下4つの書類を揃える必要があります。
| 書類の種類 | 入手・取得方法 |
|
印鑑登録証明書 |
市区町村役所の窓口で発行 (※要登録印) |
| 住民票 |
市区町村役所の窓口で発行 |
|
事業計画書 又は パンフレット |
自分で作成する |
|
代表者の顔写真付き 身分証明書のコピー |
免許証・保険証などを 自宅のプリンタやコンビニでコピーする |
法人として契約する場合
一方、法人の場合は主に下記4つが必要になります。入手場所の違いに気を付けましょう。
| 書類の種類 | 入手・取得方法 |
|
登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) |
・法務局の窓口で申請 ・交付申請書を郵送して取得 ・オンラインから申請 |
| 会社定款又は会社案内 |
・会社定款:公証役場で謄本の取得、 又は自社で保管したものをコピーする ・会社案内:自社で作成する |
| 印鑑登録証明書 |
・法務局の窓口で取得 ・郵送で請求 ・オンライン申請 (※事前に電子証明書の取得が必須) |
|
代表者の顔写真付き 身分証明書のコピー |
免許証・保険証などを 自宅のプリンタやコンビニでコピーする |
個人事業主と法人では、一部必要なものが異なります。法人は登記簿謄本と、会社定款や案内のパンフレットが求められますので、間違えないように注意しましょう。取得方法によっては時間がかかるため、スケジュールに余裕を持った行動をおすすめします。
バーチャルオフィスの契約書を公開
弊社京都バーチャルオフィスの利用申込書と利用規約です。
弊社京都バーチャルオフィスの契約書を下記にUPいたします。ポイントは不正な利用を防ぐために下記のような一文を盛り込んでいることです。
【1】取引先への未払い、税金や社会保険料の滞納を防ぐ目的
警察や税務署、債権者などから問い合わせがあった場合には個人情報を公開させていただくこともあります。
【2】バーチャルオフィス解約後、関係各所へ速やかに住所変更連絡をしてもらう目的
解約時には最終利用月の末日までに、全ての住所変更を終えてください。住所変更を証明できる書面の提出が必要です 。
賃貸借契約書の有無について
バーチャルオフィスの住所を借りて、事業を運営していると、取引先から「賃貸借契約書」を求められることがあります。「賃貸借契約書」は口座開設や融資の際に金融機関から求められるケースが多いです。
しかしバーチャルオフィスでは賃貸借契約書は存在していません。
このようなケースの場合には弊社では下記で代用いただくよう対応しております
・申込書の写し
・賃貸借契約確認書
この2つの書類をご用意いたします。長らくバーチャルオフィスを運営しておりますが、今までの全てのお客様はこの2つの書類で充分に代用できております。ご安心ください
バーチャルオフィスの契約形態は「期間貸し」か「時間貸し」
バーチャルオフィスの契約形態は、期間貸しと時間貸しの2種類に分けられます。では、どのような違いがあるのでしょうか?以下では、各契約形態の特徴やメリット・デメリットについて説明します。
期間貸しとは?
期間貸しは月または年単位で契約する形態をいいます。期間は業者によって異なりますが、始めに1ヶ月や3ヶ月、1年などの単位で契約し、その後は自動更新となることが一般的です。期間貸しはバーチャルオフィスでポピュラーな契約形態で、ほぼ全ての業者が採用しています。「バーチャルオフィス=期間貸し」と考えても差し支えありません。
◆期間貸しのメリット・デメリット◆<
期間貸しの主なメリットとデメリットは次のとおりです。
【メリット】
同期間使う場合、時間貸しよりコストを抑えられる
長期利用が前提のため法人登記に向いている
その都度契約や使用申込みをしなくてよい
【デメリット】
業者によっては最低期間がある
長期利用におけるメリットが多い反面、最低期間を設けている場合もあります。気になる方は業者へ問い合わせてみましょう。
時間貸しとは?
時間貸しは、文字通り時間制でバーチャルオフィスを貸し出している契約形態です。1時間単位で借りられるサービスが多いです。気軽に使用できることが特徴で、短時間だけ使いたい・数日だけオフィスを確保したい方に適しているでしょう。この形態に関してはどちらかと言うとバーチャルオフィスではなくコワーキングスペースなどによくみられる「ドロップイン」と呼ばれる利用方法です。
◆時間貸しのメリット・デメリット◆
時間貸しには以下のメリットやデメリットがあります。
【メリット】
コストを抑えられる
必要な時のみ利用できる
【デメリット】
対応業者が非常に少ない
コスト抑制効果が大きい反面、バーチャルオフィスで時間貸しに対応している業者はほとんどありません。もし1時間だけ使いたいような状況であれば、シェアオフィスやコワーキングスペースも検討してみましょう。
全国主要都市別おすすめバーチャルオフィス
全国のバーチャルオフィスを主要都市別にご案内していきます。各主要都市の中心部をエリア別に分けて地図とGoogleストリートビューを埋め込んでいます
京都のおすすめバーチャルオフィス

烏丸 (からすま)通とは京都市内の中心部を南北に伸びる大きな道路です。烏丸通は京都のビジネスや商業の中心であり、金融機関や京都経済センター、オフィスビルなどが立ち並んでいます。このページでは烏丸御池から四条烏丸あたりに位置する京都のバーチャルオフィスをご紹介いたします。

京都駅周辺から七条通り付近に位置する法人登記可能な京都のバーチャルオフィスをご紹介いたします。京都でバーチャルオフィスを探している方には必見の記事です。地図付き、ビルの外観写真付きです
名古屋のおすすめバーチャルオフィス

【2023年最新】名古屋駅のバーチャルオフィス20選!料金・サービス・立地など徹底比較
今回、名古屋にあるバーチャルオフィスを合計43件紹介しています。そのうちこのページでは名古屋駅(名駅)近辺のバーチャルオフィスを「中村区」「西区」2つのエリアにわけて、20件掲載しております。地図とビル外観ストリートビューを付けております。(名古屋駅20選+栄9選+その他14選=43選)

名古屋市内のバーチャルオフィスを栄を中心に一挙23選紹介!あなたにぴったりなものは?
今回、名古屋にあるバーチャルオフィスを合計43件紹介しています。そのうちこのページでは栄を中心に紹介します。栄のバーチャルオフィスを9件+その他エリア14件=合計23件掲載しております。地図とビル外観のストリートビューを付けております。
(名古屋駅20選+栄9選+その他14選=43選)
札幌市のおすすめバーチャルオフィス

札幌のバーチャルオフィス完全ガイド!厳選26施設の料金・サービス・立地の特徴とメリット
北海道札幌市にあるオススメのバーチャルオフィスを比較しながら紹介していきます。地図やビルの画像も掲載しております。札幌で起業される方はぜひ参考にしてください。「大通駅徒歩圏内17件」「札幌駅徒歩圏内3件」「大通駅、札幌駅徒歩圏外6件」3つのエリアにわけて、26件掲載しております。
福岡市のおすすめバーチャルオフィス

福岡のバーチャルオフィス完全ガイド!オススメ34選の料金・サービス・立地などご紹介
福岡市にあるオススメのバーチャルオフィスを比較しながら紹介していきます。地図やビルの画像も掲載しております。福岡で起業される方はぜひ参考にしてください。「博多駅徒歩圏内15件」「天神駅徒歩圏内13件」「博多駅、天神駅徒歩圏外6件」3つのエリアにわけて、34件掲載しております。
横浜市のおすすめバーチャルオフィス

横浜のバーチャルオフィス39選!格安・登記可能・駅近など厳選紹介
横浜市にあるオススメのバーチャルオフィスを比較しながら紹介していきます。地図やビルの画像も掲載しております。横浜で起業される方はぜひ参考にしてください。「関内~馬車道の周辺13件」「みなとみらい~桜木町周辺4件」「横浜駅周辺12件」「新横浜駅周辺4件」「その他郊外6件」5つのエリアにわけて、合計39件掲載しております。
仙台市のおすすめバーチャルオフィス

仙台で人気のバーチャルオフィス19選!オススメはここ!コスト削減でビジネスチャンスをつかむ!
宮城県仙台市にあるオススメのバーチャルオフィスを比較しながら紹介していきます。地図やビルの画像も掲載しております。仙台で起業される方はぜひ参考にしてください。「広瀬通駅の周辺3件」「仙台駅周辺13件」「その他郊外3件」3つのエリアにわけて、合計19件掲載しております。地図とビル外観ストリートビューを付けております
広島市のおすすめバーチャルオフィス

広島でビジネス拠点に最適なバーチャルオフィス17選!オススメはここ!
広島県広島市にあるオススメのバーチャルオフィスを比較しながら紹介していきます。地図やビルの画像も掲載しております。広島で起業される方はぜひ参考にしてください。「広島駅の周辺2件」「県庁前/紙屋町/八丁堀の周辺8件」「銀山町の周辺2件」「 袋町/平和大通りの周辺3件」「その他郊外2件」5つのエリアにわけて、合計17件掲載しております。地図とビル外観ストリートビューを付けております
静岡県のおすすめバーチャルオフィス

静岡のバーチャルオフィスはどこがいい?21選からあなたにぴったりの一つを見つけよう
静岡県にあるオススメのバーチャルオフィスを比較しながら紹介していきます。地図やビルの画像も掲載しております。静岡で起業される方はぜひ参考にしてください。「静岡駅の周辺7件」「新静岡駅周辺1件」「その他静岡市内4件」「 浜松市内9件」4つのエリアにわけて、合計21件掲載しております。地図とビル外観ストリートビューを付けております
千葉県のおすすめバーチャルオフィス

千葉のバーチャルオフィス24選!コスパ・立地・サービスの3つの視点で紹介
千葉県にあるオススメのバーチャルオフィスを比較しながら紹介していきます。地図やビルの画像も掲載しております。千葉県で起業される方はぜひ参考にしてください。「千葉駅の周辺10件」「海浜幕張駅周辺2件」「松戸市内4件」「 船橋市内3件」「 柏市内5件」5つのエリアにわけて、合計21件掲載しております。地図とビル外観ストリートビューを付けております
埼玉県のおすすめバーチャルオフィス

埼玉のバーチャルオフィス24選!コスパ・サービス・立地で比較
埼玉県にあるオススメのバーチャルオフィスを比較しながら紹介していきます。地図やビルの画像も掲載しております。埼玉県で起業される方はぜひ参考にしてください。「さいたま市大宮区11件」「さいたま市南区(浦和)2件」「川口市内2件」「越谷市内2件」「その他の地域7件(川越、戸田、上尾、本庄、熊谷、志木、所沢から各1件ずつ)」3つのエリアにわけて、合計24件掲載しております。
岡山県のおすすめバーチャルオフィス

バーチャルオフィスで岡山ビジネスを加速させる!注目の施設21選
岡山県にあるオススメのバーチャルオフィスを比較しながら紹介していきます。地図やビルの画像も掲載しております。岡山県で起業される方はぜひ参考にしてください。「岡山駅周辺10件」「岡山市北区表町/西大寺町2件」「岡山市北区/北長瀬2件」「岡山市その他郊外4件「岡山市外3件」5つのエリアにわけて、合計21件掲載しております。
大阪のおすすめバーチャルオフィス

バーチャルオフィスは格安で借りられることから、低コストで起業したい人に最適です。この記事では、大阪でおすすめのバーチャルオフィスを紹介します。オフィスごとに料金やプランごとの違い、サービスの詳細も掲載しています。
神戸のおすすめバーチャルオフィス

バーチャルオフィスを探している方へ!神戸のおすすめバーチャルオフィス 9選
バーチャルオフィスを探している方が特に気になるのは、取得する住所のブランド力や、利用金額、または備わっているサービスの種類ではないでしょうか?そこでこの記事では、神戸の地に焦点を絞って、おすすめのバーチャルオフィスを紹介していきます。バーチャルオフィス導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
バーチャルオフィスの契約の流れは決して難しくありません。内観を行って書類を提出し、所定の審査を受けるのみで終わります。ただし、審査で落ちるケースも極稀にありますので、準備を万全に行った上で内観を予約しましょう。また、個人・法人では契約に必要な書類も異なります。特に法人は取得に時間がかかる書類もあるため、スケジュールを立てて行動することがよいでしょう。
バーチャルオフィスなら京都バーチャルオフィス
全国には数多くのバーチャルオフィスがありますが、京都でお探しなら京都バーチャルオフィスへお任せ下さい。弊社ならではの強みや、実際に利用されているお客様の声をご紹介します。
京都バーチャルオフィスの特徴
京都バーチャルオフィスの強みは以下のとおりです。
・サービス内容に応じて選べる4つのプラン
・京都御所から徒歩1分の好立地
・月額2,000円〜!エリア最安値に挑戦中
・電話番号取得・転送サービス付きでも月額6,500円〜
・商談スペースもあり
特に月額料金の安さには自信があります。もし低コストで開業したい、初期費用を抑えたいとお悩みなら、ぜひ弊社にご相談下さい。
【他社よりも格安でサービスを提供できる理由】
バーチャルオフィスの多くはレンタルオフィスも併設しています。レンタルオフィスとは、デスクや会議室も提供するサービスです。この場合には広い敷地・面積を有する物件が必要になります。また受付や清掃のスタッフも雇用する必要もありますね。しかし当社はデスク・会議室のサービスを排除し、私書箱機能・住所貸し・電話 転送・Fax利用に限定し、発生する経費を削減し、業界最安値を実現いたしました。もちろん来客時の商談スペースは設けておりますのでご安心ください
京都バーチャルオフィスを利用したお客様の声
実際に京都バーチャルオフィスをご利用いただいているお客様の声をご紹介します。以下のお客様は大阪からご利用頂いています。
【ご利用プラン】スタンダードプラン
寝屋川に住んでいて、事務所も借りていないのに京都市内の最高の立地で、起業をスタートできたことは本当によかったです。現在は、私一人なら充分に食べていけるようになり、当時の独立前にいたブラック企業の同僚からもうらやましがられ、起業を薦めているくらいです。”(T.M様 男性)
京都バーチャルオフィスのプラン内容
京都バーチャルオフィスでは、以下4つのプランをご用意しています。それぞれの料金とサービス内容は次のとおりです。
| プラン名 | 料金/月額 | 主なサービス |
| エコノミー | 1,500円 |
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便受け取りと転送なし ・ポストへ社名表示なし |
| スタンダード | 3,500円 |
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の転送 |
| ビジネス | 6,500円 |
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の転送 ・電話番号取得・転送 ・スマホから市外局番通知可能 |
| プラチナ | 11,000円 |
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の転送 ・電話番号取得・転送 ・スマホから市外局番通知可能 ・FAX利用・転送 ・商談スペース (月10時間まで無料) ・フリーダイヤル利用 |
このように、プランごとに料金やサービス内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選び頂けます。どのプランが適切か悩んだ際は一度ご相談下さい。京都バーチャルオフィスでは、適切なプランをご提案し、皆様のビジネスをサポートいたします。

京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは
京都バーチャルオフィス
あなたへオススメの関連記事
この記事を読んだ方には下記ページもよく読まれています

バーチャルオフィスは小規模事業者にとってビジネス上、様々なメリットがあります。どんなメリットがあるのか?確認していきます。さらにバーチャルオフィス自体をビジネスとして開始するためのポイントや将来性も併せて考察してみます。

どうしてバーチャルオフィスの利用審査は厳しいのでしょうか?一見不要にも思えますが、犯罪者収益防止法が関わるため審査はとても厳格となっています。手軽に住所や電話番号を取得できるというサービスの性質上、不正や犯罪に利用されやすいという側面があります。

せどりとは簡単に言うと古本屋などで商品を安く仕入れてネットで高く売ることです。由来は、転売業者が古本屋で本の背表紙を見て買う本を選んでいたことだと言われています。数年前からこのせどりが副業として定番になっています。