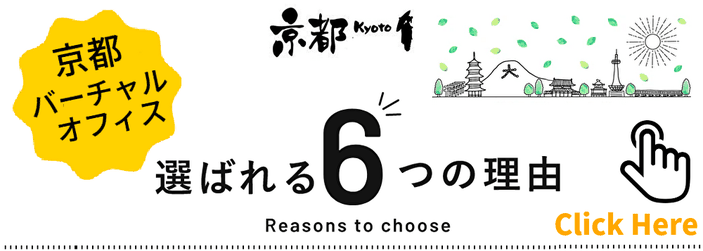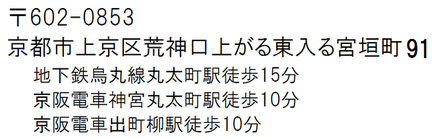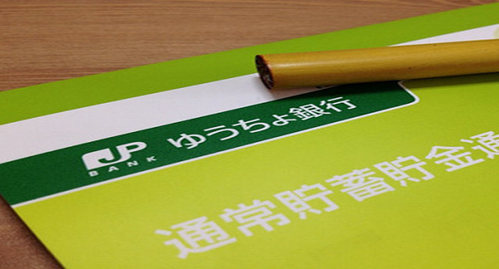落とし穴がある?バーチャルオフィスを利用する前に知っておくべきリスクと7つの注意点
HOME > バーチャルオフィスとは? > 注意点
起業する際にはとても便利なバーチャルオフィス。でもそんな便利なサービスにも利用において注意点があります。この記事では利用における注意点を開設します
バーチャルオフィスとは?
独立して起業しよう!サラリーマンの給料だけでは不安だから副業をしよう!こんな方へピッタリなのがバーチャルオフィスサービスです。とはいえ実際に利用したこともないので、どんなサービスなのかわかりにくい方もいるはずです。まずは、なぜ起業や副業にバーチャルオフィスが向いているのかを説明いたします。
*簡単に言うと仮想の事務所
バーチャルオフィスとは、実際のテナント・不動産を賃貸するのではなく、入居もせずに、オフィスとしての最低限の機能、住所や電話番号だけを利用できるサービスです。バーチャルオフィスというキーワードが示すようにまさに「仮想の事務所」を意味します。
仮想の事務所とはいえ、住所を名刺やパンフレットに表示、市外局番の固定電話番号を利用できるだけでなく、仮想オフィス宛に届いた郵便物を受け取り、希望の住所へ転送してくれたり、会議室や作業スペースなどを時間単位で借りたりできるのがバーチャルオフィスも多くあります。
*起業時に人気のバーチャルオフィス
ベンチャービジネスでの起業・法人化せずに小規模事業者での開業、フリーランス、さらにサラリーマン副業など、規模や形態は異なれど、自分のビジネスを始める方はどんどん増えてきています。バーチャルオフィスは、実際に作業を行う事務所を必要としない方、経費を節約したい方には非常に便利なサービスなのです。
*初期費用・固定費を抑えられるバーチャルオフィス
起業するときに拠点となる「オフィス」をどのように用意するのか?しっかりと検討しておくべき課題です。最初から実際のテナントを賃貸したり、レンタルオフィスなどを利用して作業スペースを確保すると、物件探しや契約手続きなどに手間がかかり、さらに敷金礼金・デスクや椅子など初期費用・入居後の月額賃料や光熱費・通信環境などの固定費が発生します。
これは売上が見込めない起業直後には大きな負担となり、資金ショートしてしまう要因になります。PCを使った実務などを行う作業スペースは、自宅の一室やカフェなどで事足りる業種の方は、起業直後には自宅兼事務所にて事業を始めるのが得策なのです。
*プライバシーを保護できるバーチャルオフィス
しかしこの場合においても、自宅住所を本社所在地として登記したり、ホームページや名刺などで一般に公開したくないのが本心です。さらに賃貸住宅の場合、オフィスとしての利用が禁止されていたり、登記不可という契約がほとんどなのですこんな起業家の悩みを全て解決できるのがバーチャルオフィスなのです。
まずはバーチャルオフィスのメリットを整理
起業時や支社設置のときに、とても便利なバーチャルオフィス。格安で使えることはもちろん。お申込から約1週間程度で利用が開始できるスピードもとても魅力的です。
【バーチャルオフィスのメリット】
・とにかく格安
・自宅住所を公開しなくていい
・法人所在地として登記できる
・すぐに使える(申込から約1週間程度)
京都バーチャルオフィスは来店不要で契約が可能。書類の郵送、メール電話でのやりとりのみですので利用開始まで最短で3~4日程度の所要時間でございます。
しかしその反面、物理的な空間を実際にオフィスとして利用するわけではないので、場合によってはいくつか注意点・問題点も抱えています。
何も知らずにバーチャルオフィスを契約して、いざ利用が始まってから、不便なことに気づいてしまうこともありがち。メリットだけでなく事前にデメリットもしっかり把握しておきましょう。
バーチャルオフィス利用の注意点やリスク
ここでは実際にオフィスを借りる場合と比較して、バーチャルオフィスを利用したときには、どのような注意点があるのか?解説いたします
【1】他社と住所が重複
多くの利用者が同じ住所を利用します。これはインターネット上に所在地を記載したとき、ユーザーが所在地で検索すると、同じ所在地がたくさん表示されてしまいます。バーチャルオフィスに限ったことでなく、レンタルオフィスやシェアオフィスでも同じことが言えるでしょう。つまりバーチャルオフィスだとバレてしまう可能性があります。
【京都バーチャルオフィスの場合】
当社では対策として、全てのお客様に出来る限り、画像処理にして住所を掲載いただくように御願いしておりますが、強制はできないため、完全な対策とは言えません。
しかし京都市内での住所をバーチャルオフィスとして利用する場合には他の都道府県と比較して、バレにくいと言えます。
【2】世間の信用 / 逆に怪しい?
バーチャルオフィスでは一等地の住所を借りることができます。しかし初めて起業したにも関わらず一等地に事業所を構えると、かえって怪しいと映るかもしれません。例えば起業したばかりなのに、いきなり六本木ヒルズや東京ミッドタウン、グランフロント大阪など著名な建物に会社を構えることは通常はしません。かなりの資金力をもって起業しない限り不可能です。
【京都バーチャルオフィスの場合】
弊社の所在地は京都でも有数の一等地(京都御所徒歩1分)ではございますが、まず繁華街ではございません。そして大型の商業施設でもございません。
【3】銀行口座開設
銀行や支店によって審査基準は異なりますが、バーチャルオフィスの住所を利用して銀行口座開設を申し込むと断られる場合があります。
これまでバーチャルオフィスの住所を悪用した詐欺が発生しており、新規で口座開設する会社に対し、警戒を強めているのが理由の1つです。
バーチャルオフィスを契約する前に、バーチャルオフィスを利用した口座開設が可能かどうか、利用を申し込む前に、金融機関に確認しておくことをおすすめします。
【京都バーチャルオフィスの場合】
京都バーチャルオフィスでは、お客様宛の銀行からの郵便物が頻繁に届いております。したがって問題なく口座開設できている方がほとんどだと言っていいでしょう。弊社の利用者の傾向から言いますと、新規口座を開設しやすいのが地銀や信用金庫、そして何と言ってもネットバンクですね。
弊社バーチャルオフィスでは利用前に顧客信用調査を徹底しており、申込者の10%程度は利用をお断りしております。それでも全ての同業者が調査を徹底しているわけではないため、バーチャルオフィスと言うだけ口座を開設させてもらえない金融機関があることは事実です。
【4】起業に必要な許認可関係
バーチャルオフィスを利用しても、事業内容によっては起業に必要な許認可を満たさないことがあります。一般派遣業や建設業、出張型の飲食業、税理士や司法書士などの士業、不動産業などは注意が必要です。
バーチャルオフィス契約後に許認可を満たさないと分かれば、起業に遅れが生じ、余分な費用もかかります。許認可に関して不安な点があれば、行政書士や社会保険労務士などに相談しましょう。
【5】創業融資が受けにくい?
自治体や金融機関などから融資を受けたい場合、バーチャルオフィスの住所を使うと審査に通らないケースがあります。事業の実態がないとされる可能性があるため、融資を受けたい場合も税理士などに相談すると良いでしょう。バーチャルオフィスの中には融資の相談や、創業融資に必要な書類の準備をサポートする所もあるため、上手く活用することをおすすめします。創業融資に関しては日本政策金融公庫をオススメしています。
【京都バーチャルオフィスの場合】
弊社のお客様の中には数名、創業融資を受けることができた方がいらっしゃいます。バーチャルオフィスだと実際にオフィスを賃貸している方と比べると創業融資を受けにくいのは事実です。しかしその反面、経営者としてしっかりとリスク管理を行い、会社経営にとってもっとも負担になる固定費を削減できているという受け止め方もできます。
このようなメリットの部分をしっかりと説明すれば創業融資を受けることも可能です。また京都バーチャルオフィス代表の松村は商工会議所青年部の理事として活動しております。京都市での創業融資についてお気軽にご相談ください
【6】荷物受け取りが少し遅くなる
事業によっては書留郵便やクール便、大きな荷物が届くこともあるでしょう。中にはそういった荷物の受け取りを行っていないバーチャルオフィスもあるため、注意が必要です。
取り扱っている荷物の受け取りや保管が可能かどうか、契約前にチェックしましょう。
さらに早く受け取りたい書類や荷物がある場合に、1日~2日程度受け取りが遅くなってしまうという性質もございます。
荷物がバーチャルオフィスへ到着後、バーチャルオフィスからご希望の住所へ転送するため、1~2日程度のタイムラグが生じるのが理由です。どうしても早く受け取りたい荷物があり、送り主からご自宅へ直接郵送してもらっても問題ない場合は、直接郵送してもらうように御願いしてみてはどうでしょう。
【7】商談・ワークスペースを別に確保する
仕事をするための物理的な空間がないため、自宅やカフェでワークスペースを確保する必要がある。これがバーチャルオフィスのもっとも大きな特徴です。したがって今さらデメリット部分に記載する必要もないかもしれません。近年、インターネットが発達したことにより、ノマドワーカーなどが登場し、従来の働き方に変革がおこっています。物理的スペースは来客時など以外には必要なくなっています。充分に自宅で仕事をすることは可能になってきています。
打ち合わせや会議ですら、SkypeやLINEなどのテレビ電話機能があれば、全く問題ないですよね。
京都バーチャルオフィスへのGoogle Mapでの口コミ

【Google mapの口コミ1】
追加料金が一切ないところが魅力的なので、使い始めてから5年ほど経ってますが、ずっとここ使い続けるつもりです。
いろいろ調べた結果、この値段で郵便物の無料転送サービスまでついているのはなかなか他にはないです。 住所もとても良い立地で京都の一等地です。もちろん対応も丁寧で早いです。そんなわけで安心して利用できるのでおすすめのオフィスです
【引用元】
【Google mapの口コミ2】
起業するのは初めてで、わかならいことだらけでした。
住所や電話番号のレンタルだけでなく、ビジネスや税務、集客、会社の設立のことなどアドバイスももらいました。
値段も手ごろで、作業する場所が必要ない人にはとてもオススメかなと思います
【引用元】
【Google mapの口コミ3】
法人登記の手続きにはこちらの住所を使っていて、既に4年程度利用していますが、とても満足しています。
対応が素早く、丁寧で大変助かっています。わたしからの急ぎの要望にも休日でも柔軟に対応していただき、本当に感謝しています
【引用元】
【Google mapの口コミ4】
京都へ会社を移転したときからつかっています。
私はパソコンでFAXが使えるプランにしております
ほぼほぼ一人で事業をやっている私には使い勝手の良いサービスです。
郵便物の対応もとても丁寧で迅速です。
重要な荷物の引き取りは休日でも対応いただいたこともあります。
人を紹介してほしいなどの相談にもしっかり乗ってくれますよ。
【引用元】
【Google mapの口コミ5】
会社設立時から本店所在地として使わせてもらってます。
わたしの場合は実際にオフィスに行くことがほぼないので
コワーキングスペースよりも住所貸しに特化した京都バーチャルオフィスで充分でした。
導入費用もランニングコストも圧倒的に抑えられています。
問い合わせのときの対応もとても気持ちよく、ここに決めました。
他にも安いところはありましたが、郵便転送などをお願いすると結局は高くなってしまうので、
書類転送無料の京都バーチャルオフィスが結局は安いのかなと思います。
【引用元】
【Google mapの口コミ6】
アドレスも京都の有名な地名で取引先からの信頼も大きいようです。
市外局番が使えるスマホアプリではフリーダイヤルも使わせていただいてます
突然の無理なお願いにも、いつでも気持ちよく対応してくれます。
書類の転送がタダなので月々の料金の計算も不要で、わかりやすいのが魅力です
【引用元】
【Google mapの口コミ7】
申し込みから契約までがスムーズでした。他社と比較して立地、値段、サービスからここに決めました。審査もちゃんとやってるみたいで安心できました
【引用元】
【Google mapの口コミ8】
親身になって集客の相談に乗ってくれました。熱い思いが伝わってきて起業を頑張る気持ちになれました
ここは賃貸でされてなくて、所有している物件でやってるみたいで安心です。
無人のバーチャルオフィスが他にはあるようですがここは有人でやってるところも決め手になりました
【引用元】
【Google mapの口コミ9】
専用電話番号利用のプランをつかってます
090の携帯や050番号だと信用力も低いと思うので・・・
京都の075市外局番がスマホのアプリから通知できるのが
かなりのおすすめポイントです。
【引用元】
【Google mapの口コミ10】
いつもお世話になっております。
痒いところに手が届くサービスでとても助かってます。
これからもよろしくお願いします。
【引用元】

京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは
京都バーチャルオフィス
あなたへオススメの関連記事
この記事を読んだ方には下記ページもよく読まれています

運営会社それぞれのHPを見て、よし!実際に利用して起業しよう!そう思った方へ。一般的な利用開始までの流れや必要な手続きを詳細に説明します。利用のためには提出するべき書類がいくつかあります。もちろんオフィスを実際に賃貸するよりははるかに簡易な手続きです。またバーチャルオフィスの使い方や一般的な費用、レンタルオフィスとの違い、銀行口座開設、ネットショップで必要な理由などなどもまとめて解説いたします。

バーチャルオフィスは小規模事業者にとってビジネス上、様々なメリットがあります。どんなメリットがあるのか?確認していきます。さらにバーチャルオフィス自体をビジネスとして開始するためのポイントや将来性も併せて考察してみます。

起業したばかりで、あまり人脈もない場合、取引先をゼロから開拓していかなくてはなりません。それは税理士など士業の先生を探す場合も同じです。かといって全く知らない方に依頼するのも少し不安です。そんなときに様々な会社や士業を紹介してくれるのがバーチャルオフィスです。