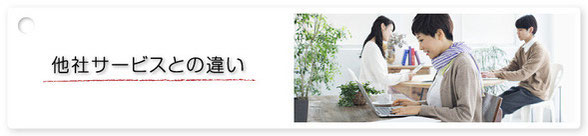京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは
バーチャルオフィスは違法?法人登記に利用できる?利用できない業種や注意点5つを紹介
HOME > バーチャルオフィスとは? > 違法
バーチャルオフィスは格安で登記ができる一方、匿名性の高さから悪用されるケースがあるのも実情です。このため違法ではないかと懸念を持つ人も中にはいますが、本当にそうなのでしょうか。この記事では、現在バーチャルオフィスを検討中の方を対象に、違法性やバーチャルオフィスで可能なこと、メリットやサービスを選ぶポイントなどについて解説します。
バーチャルオフィスは違法ではありません!
先に触れておきますが、バーチャルオフィスそのものは決して違法ではありません。後述するように違法となる業種も中にはありますが、ほとんどの業種は何の問題なく契約できます。
商業登記法上、本店所在地に関する制限はない
商業登記法上は会社設立時の本店所在地住所に関する制限はないので、自宅、知人のオフィス、居住している賃貸マンション、倉庫などどこの住所を使っても法務局への法人登記の申請は可能です。
違法性を問われる理由としては、現在は比較的少なくなったと言われているもののバーチャルオフィスを悪用した詐欺事件が過去には多くあったことが挙げられます。各事業者は、利用所の事業実態と本人確認の徹底によりこれを防止し、健全なバーチャルオフィス事業運営に努めています
バーチャルオフィスで法人登記もできます!
バーチャルオフィスは法人登記もできますが、バーチャルオフィスを利用した法人登記は年々増加しており、今後も市場が拡大していくと考えられています。
バーチャルオフィスによる法人登記が増えている理由は、主に以下が挙げられます。
・テレワークの増加により物理的なオフィスが不要になった
・フリーランスとして独立開業する人が増えた
(特商法への表記や会社立ち上げ時に登記で使う)
・コストを抑えて一等地に登記したいと考える人が多い
従来どおりコストを抑えつつ、一等地で登記したいという理由もバーチャルオフィスの需要を加速させています。一方でテレワークによって物理的なオフィスが不要になったケースや、独立開業したフリーランスの増加も背景にあります。
バーチャルオフィスでできること

バーチャルオフィスは単に住所を貸し出すだけではありません。契約すると、下記のようなサービスを利用できる場合があります。
・郵便物の受取・転送
・専用電話番号やFAX番号の使用
・電話転送や受付代行
・ミーティングスペース・会議室のレンタル
・法人登記代行
・来客の対応
・税務や会計業務の代行
これらの他にも、ホームページの制作や自社看板の作成、無料のOA機器やWi-Fiなど、独自のサービスが提供されています。バーチャルオフィスごとに内容は変わりますので、契約前に確認しておくとよいでしょう。
バーチャルオフィスを使用できない職種も・・

一方でバーチャルオフィスを利用すると違法になってしまう業種も存在します。以下で問題のない業種やNGの業種、違法になる理由について解説します。
バーチャルオフィスを利用しても問題のない業種や法人格
バーチャルオフィスを契約すべきか悩んでしまうかもしれませんが、以下に該当するのであれば、契約しても法的に違法性を問われる心配はありません。
・通常の株式会社や合同会社、合資会社
・一般社団法人
・財団法人
・NPO法人
通常の株式会社はもちろん、社団法人や財団法人、NPOもバーチャルオフィスの利用が可能です。登記や名刺に住所を利用しても問題がないため、コストを抑えながら各種法人を設立できます
バーチャルオフィスを利用すると違法な業種
反対に以下へ該当する業種の場合、バーチャルオフィスの利用や登記は違法となります。該当する業種の場合は、通常のオフィスなどを契約しましょう。
<人材派遣業>
人材派遣業は、開業時に20平方メートル以上の事務所やオフィスを契約していることが求められます。バーチャルオフィスは住所のみを借りるため、人材派遣業の開業条件を満たせません。もし人材派遣業を起業する場合、通常のレンタルオフィスを利用しましょう。規模に関わらず、バーチャルオフィスで起業すると違法になってしまいます。
<有料職業紹介業>
職業紹介業も実体のあるオフィスや事務所が必要です。バーチャルオフィスは実体を持たないため、認可をもらえません。人材派遣業の場合と同じで、職業紹介業も賃貸オフィスや事務所の契約が求められます。面談スペースなどが欠かせないため、そもそもバーチャルオフィスは開業条件を満たせない点に注意が必要です。
<士業>
士業も登記や認可が難しい業種の一つです。士業は依頼主と面談するスペースなどが必要な反面、バーチャルオフィスは賃貸借契約書の発行も難しく、事務所の実体確認ができません。士業がバーチャルオフィスを事務所として登記した場合、以上の理由から違法となってしまうおそれがあります。
<探偵業>
探偵業もバーチャルオフィスでは開業できません。士業と同じく事務所の実体がないためです。なお、探偵業を始める時は公安委員会へ届け出をしなくてはいけません。しかし事務所の実体がないため、届け出を受理してもらえない可能性が高いです。
<建設業>
建設業も実体ある事務所やオフィスが求められます。都道府県により認可基準が異なるものの、バーチャルオフィスは実体がないと判断され、認可を受けられないケースがほとんどです。
<不動産業>
不動産業は、開業時に宅地建物取引業免許の取得が求められます。しかし、宅地建物取引業免許の取得には実体のある事務所が必要なため、バーチャルオフィスは開業条件を満たせません。
<中古品販売・リサイクルショップ>
中古品販売・リサイクルショップを開業したい人も、バーチャルオフィスの利用は諦めましょう。確かに古物商の認可があれば開業はできるものの、認可を取ることが難しく、開業が不可能に近いのが実情です。なお、古物商の認可を得ずに営業すると古物営業法違反となり、罰則や行政処分の対象になります。大きなペナルティを受けるため、開業時は必ず実体あるオフィスや事務所を賃貸しましょう。
<不用品回収業>
不用品回収業もバーチャルオフィスを使って開業することはほぼ不可能です。登記のみに使う方法も考えられますが、事務所の実体がないと古物商や一般廃棄物収集運搬業の認可が下りません。中古品の販売業やリサイクルショップと同じく、開業時は賃貸のオフィスや事務所を利用しましょう。
<金融商品取引業者>
金融商品取引業者は登録が必要なうえ、金融商品取引業者登録票を事務所に提示しなくてはいけません。この時点でバーチャルオフィスは実体がなく、開業は非現実的であるといえます。
また、金融商品取引業者登録票を取得する際は、事務所・オフィスの賃貸借契約書が必要です。実体がないバーチャルオフィスは賃貸借契約書の発行が難しいため、金融商品取引業者登録票の取得そのものが実質不可能です。
<風俗業>
ここでいう風俗業とは、パチンコ店やゲームセンター、バーなど、風俗営業許可が必要な業種を指します。性風俗に関する業種とは異なる点に注意しましょう。風俗業の多くは実店舗が必要で、各店舗ごとに立地などの諸条件を満たし、営業認可を得なくてはいけません。バーチャルオフィスはあくまで住所を貸すのみですので、風俗業を開業すると違法となります。
バーチャルオフィス利用時の注意点

上記のように、バーチャルオフィスが違法になる業種も少なくないですが、上記に挙げた職種以外の問題がない業種でもいくつか注意すべき点があります。
ネットショップを運営する場合は違法になることもある?

ネットショップを運営している場合、バーチャルオフィスの利用方法次第では違法になるおそれまではなくとも各モール(amazonや楽天、ヤフーショッピングなど)の規約違反になることはありえます。
例えば利用者から情報開示請求があった場合、ショップ側は販売者の名前や住所、連絡先などの情報を開示しなくてはいけません。しかし、問い合わせに対してバーチャルオフィスの住所を教えてしまうと、実際の販売者の情報と異なることから、規約違反になるおそれがあります。
もしサイト上にバーチャルオフィスの住所を記載するのであれば、その旨をページ内に明記するか、特定商取引法に沿った正しい情報を表記することが大切です。ネットショップ開設の際に利用する各モール(amazonや楽天、ヤフーショッピングなど)の規約を確認したほうが無難だと言えます
無許可の住所貸しはトラブルになる原因になりやすい
契約しようとしているバーチャルオフィスが家主などに無許可で住所貸しを行っている可能性もあります。トラブルにもつながりますので、そのバーチャルオフィスが安全に利用できるか、しっかり確認してから契約を判断するべきです。なお、考えられる事例として以下のようなものがあります。
・ビルなどの大家に内緒で住所貸しを行っている
・知人や友人の賃貸物件を登記用に使用している
このような行為を行っている業者の場合、必ず契約は避けましょう。違法性が非常に高いため、自身の事業にも悪影響が及ぶ可能性があります。弊社、京都バーチャルオフィスは自社物件で運営しているため、こういった心配には及びません
他の利用者にも注意
他の企業と登記住所が被ってしまう点も注意が必要です。住所が被る理由は、都心などの一等地に登記できる点や、企業の信頼性を高められる点が挙げられます。特に人気のエリアでは、登記住所が被る可能性が高くなります。このことを充分に理解した上で利用しましょう。利用にあたり以下に注意しておきましょう。
・事前にバーチャルオフィスである旨を取引先などに伝える
・ビルの入り口に自社看板を掲げてもらう
・受付で来客対応をしてくれるバーチャルオフィスを選ぶ
バーチャルオフィスを契約する際は、住所が被ることを念頭に置いて利用しましょう。近年ではバーチャルオフィスの社会的認知度も徐々に高くなってきているため、取引先などに事前に伝えておいても、よいかもしれません。
法人への金融機関からの融資・法人保険の申請

法人への融資や保険の申請に影響が及ぶ点もネックといえます。バーチャルオフィスで登記をすると、住所が他の企業と被ってしまうため、銀行融資や保険の手続きにおいて審査に時間がかかったり、追加書類を求められたりします。また、審査に落ちる可能性もあるため注意が必要です。少しでもスムーズに手続きを進めるためにも、バーチャルオフィスでも申請に問題はないか事前に確認しておきましょう。
バーチャルオフィスのメリット

バーチャルオフィスにはさまざまな注意点がある一方、契約することで受けられるメリットも少なくありません。では、どのようなメリットがあるのでしょうか?
経費節約
まず挙げられるのが初期コストや経費の削減です。バーチャルオフィスは契約時の初期費用がほとんどかからないため、起業時の出費を最小限に抑えられます。
契約後もレンタルオフィスより人件費や家賃、設備費などの費用を抑えられます。起業時に物理的なオフィスが不要で、かつコストを抑えたい人にとって、バーチャルオフィスを契約するメリットは大きいといえます。
都心一等地の住所を保有できる
バーチャルオフィスは一等地の住所を提供していることが多いため、一等地に法人登記したい人や住所が欲しい人に適しています。
バーチャルオフィスが一等地の住所を提供している理由は、企業の信頼性を高めたい、見栄えをよくしたいと考える人が一定数いるからです。特に企業の信頼性を住所で判断するパターンは多いため、理にかなっているといえるでしょう。
サービスを必要に合わせて利用できる
バーチャルオフィスは幅広いサービスを利用できる点もメリットといえます。例えば郵便物の受取や転送はもちろん、業者によっては来客対応や秘書代行などのサービスを提供しています。
他にもさまざまなサービスがあり、有料で追加できるバーチャルオフィスも少なくありません。ただし、色々なサービスを付加すると料金が高くなるため、事前に費用の見積もりを取っておきましょう。
起業準備がスピーディーに出来る
起業するまでの時間は最小限に抑えたいところですが、バーチャルオフィスを選べば時間の節約効にもつながります。契約〜利用までの流れが非常にシンプルで、審査にもさほど時間がかからないためです。1日でも早く起業したい、準備の時間を省きたいと考える人は少なくないでしょう。もし当てはまるのであれば、バーチャルオフィスを使って起業を進めるべきです。
なお、敷金や礼金などの費用がかかる業者はめったにありません。保証金は求められる場合があるものの、少額で済むため、別途融資を受ける必要性は低いといえます。
プライバシーの確保
個人事業や小規模法人の場合、自宅を登記住所にするケースも珍しくはありません。しかし、プライバシーに不安が残りますし、ネット上に住所が漏れ出し、何らかのトラブルに巻き込まれる危険も潜んでいます。バーチャルオフィスの住所は法人の登記などに使えます。自宅の住所を登記したくない人はもちろん、何らかの事情でできない場合にも最適です。
プライバシーを確保できる点でいえば、バーチャルオフィスほど手軽な方法はありません。
法人登記を行える
上記で触れたように、法人登記に利用できることもメリットといえます。低コストで起業したい人にとっては特に大きな利点となるでしょう。なお、登記するまでの大まかな流れは以下のとおりです。
1 社名・商号の決定
2 定款を作成と公証役場での認証
3 バーチャルオフィスを契約する
4 会社の登記に必要な書類を集める
5 バーチャルオフィスの住所で登記する
社名を決めたり、定款を作ったりする点は一般的な起業と同じ流れになっています。ただし、登記前にバーチャルオフィスを契約する必要があるため、早めに手続きしておきましょう。
信頼できるバーチャルオフィスの見分け方

バーチャルオフィスはどの業者でも安心して契約できる、とは限りません。危険性の高い業者も中にはありますので、慎重に選ぶ必要があります。以下では信頼できるバーチャルオフィスを見分ける方法を紹介します。トラブルを避けるためにも、一度チェックしてみて下さい。
本人確認や審査を実施しているか
まず本人確認や入居審査を行っているか確認してみましょう。
犯罪防止の観点から、バーチャルオフィスは犯罪収益移転防止法という法律の特定事業者に指定されています。主な事業が住所の貸し出しであり、犯罪に利用されるおそれがあるために厳格な本人確認・入居審査が求められています。反対に本人の確認が不要だったり、入居審査がなかったりする業者は危険性が高いため、契約は避けることをおすすめします。
運営者と利用者が顔を合わせる機会があるか
現在はさまざまな手続きがオンラインや郵送で済ませられる時代ですが、バーチャルオフィスに関しては、業者と顔を合わせる機会があるか確認したほうがよいでしょう。対面契約の可否はもちろん、オフィスの内見や見学が可能かチェックするべきです。
バーチャルオフィスは仮想的なサービスとはいえど、オフィスを借りることに違いはありません。もし業者が内見や見学を断るようであれば、契約は見送るのが賢明でしょう。対面契約も見学・内見も断る業者は実体がつかめず、信頼性に疑問が残ります。
バーチャルオフィス住所を利用しての法人登記について
あなたはバーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所で法人登記をお考えですか?もしそうなら、バーチャルオフィス住所での法人登記について知っておくべきことがあります。ここでは、法人登記の費用や流れ、バーチャルオフィス住所での法人登記のメリットやデメリットをご紹介します
【1】法人登記の初期費用はどれくらいかかる?
法人登記とは、会社や法人を設立する際に必要な手続きです。
法人登記をすることで、会社や法人が法的に認められ、税務や金融などのビジネスが円滑に行えるようになります。法人登記には、以下のような費用がかかります。
一般的に多くの起業される方が設立される「合同会社」と「株式会社」に分けて説明します
法人登記費用とは、会社を設立する際に必要な手数料や税金のことです。法人登記費用には、以下のようなものが含まれます。
【登録免許税】
会社の資本金額に応じて変わります。
・合同会社→6万円
・株式会社→最低15万円~最高60万円。
【定款認証費用】
定款を公証役場で認証するために必要な費用です。
・合同会社→不要
・株式会社→5万円
【定款印紙代】
定款に貼る収入印紙の代金です。
・合同会社→不要
・株式会社→4万円
【その他の費用】
印鑑証明や登記事項証明書などの発行費用や郵送費用などで、数千円から数万円程度です。
また、司法書士などの専門家に依頼する場合は、その報酬も別途必要です。報酬は依頼内容や業者によって異なりますが、一般的には10万円から30万円程度です。
法務局のホームページや法務局での無料相談を利用すると専門家への依頼なしで、ご自身でも対応可能です
【まとめ】
以上から法人登記費用の合計金額
合同会社の場合→約7万円から10万円程度
株式会社の場合→約20万円から25万円程度。
【2】法人登記の流れ
法人登記の流れは以下のようになります
STEP1 / 会社概要の決定:
商号や発起人、取締役や事業目的などを決めます
STEP2 / 類似商号の確認:
同じ所在地に同じ商号がある場合は登記できませんので、事前に確認します
STEP3 / 事業目的の適否確認:
事業目的が特定行政庁から許可や認可を受ける必要がある場合は、その手続きをします
STEP4 / 法人用印鑑の作成:
会社印と代表者印を作成します
STEP5 / 定款の作成:
会社の基本的な規則を定めた書面を作成します
STEP6 / 定款の認証:
作成した定款を公証役場で認証してもらいます(合同会社不要)
STEP7 / 資本金の支払い:
発起人が定款に定めた資本金を支払います
STEP8 / 登記申請書類の作成:
必要な書類を作成します。司法書士などに依頼する場合は任せることもできます
STEP9 / 法人の印鑑登録:
作成した印鑑を法務局へ印鑑登録します
STEP10 / 登記申請:
作成した書類と共に所轄の法務局へ登記申請をします。オンラインでの申請も可能です
STEP11 / 登記完了:
登記申請から1週間から10日程度で登記が完了します。登記完了後に登記簿謄本や法人印鑑証明書などを取得します。
【3】バーチャルオフィス住所での法人登記のメリット
◆低コスト◆
バーチャルオフィス住所は、実際に作業スペースを使用しないので、家賃や光熱費などのコストがかかりません。月額数百円から数万円程度で利用できます。
◆スピード◆
バーチャルオフィス住所は、物件探しや賃貸借契約などの手間がかからず、すぐに準備できます。早ければ1週間程度で利用できます。
◆プライバシー保護◆
バーチャルオフィス住所は、自宅住所を公開しなくて済むため、プライバシーの問題を気にする必要がありません。しつこい営業やクレームなどで自宅への訪問を回避できます。
【4】バーチャルオフィス住所での法人登記のデメリットと注意点
◆運営会社によって法人登記を不可◆
バーチャルオフィス運営会社によっては、法人登記を許可していない場合があります。契約前に確認しましょう。
◆複数の企業や個人で住所を共有◆
バーチャルオフィス住所は、複数の企業や個人で共有することになります。対外的に誤解を招いたり、信用に影響が出る可能性があります。
◆運営会社の倒産◆
バーチャルオフィス運営会社が倒産したり廃業したりした場合には、レンタルしている住所を返却しなければならず、本店移転をしなければならないリスクがあります。
◆働く場所を別途確保◆
バーチャルオフィス住所では、作業スペースや打ち合わせスペースが利用できないことが多いです。別途コストがかかる可能性があります。
◆許認可が受けられない?◆
バーチャルオフィス住所では、許認可を得て行う事業や事業所要件を満たさなければならない事業には向いていません。事業内容によっては不適切と判断される可能性があります。
【5】格安で法人登記に利用できるオススメの京都バーチャルオフィス
▶京都のバーチャルオフィスが他府県のユーザーからも選ばれる理由

【京都バーチャルオフィス10の特徴】
京都バーチャルオフィスは、京都御所の近くにあるバーチャルオフィスサービスです。バーチャルオフィスとは、実際に物理的なオフィスを持たずに、住所や電話番号、受付や会議室などのオフィス機能を利用できるサービスです。もちろん格安で登記可能です!!
京都バーチャルオフィスの特徴は、以下のようなものがあります。
【1】住所利用や法人登記が格安でできる
【2】郵送物を受け取ってもらえる
【3】書類に限り無制限で転送無料
【4】少人数の打ち合わせスペースの利用ができる
【5】スマホで固定電話が使えるアプリがある
【6】料金プランが豊富でリーズナブルである
【7】基本料金0円プランがある
【8】オンラインで簡単に申し込みや管理ができる
【9】自社物件で運営しているので倒産リスクがない
【10】利用できる住所は京都御所徒歩1分の好立地
京都バーチャルオフィスは、在宅勤務やリモートワークが増えた現代において、多くの企業や個人事業主にとって魅力的な選択肢となっています。京都の歴史や文化に触れながら、ビジネスを展開したい方におすすめです。詳しくは下記をご覧ください
まとめ
バーチャルオフィスのサービスそのものは決して違法ではありません。実際に登記に利用している法人も多いですし、低コストという点に注目し、開業時に利用する起業家も多数います。ただし、業種によっては違法になってしまったり、諸々の認可が下りない可能性があります。契約を検討中の人は、開業する業種でバーチャルオフィスの利用可否を確認しましょう。
バーチャルオフィスなら京都バーチャルオフィス
全国には数多くのバーチャルオフィスがありますが、京都でお探しなら京都バーチャルオフィスへお任せ下さい。弊社ならではの強みや、実際に利用されているお客様の声をご紹介します。
京都バーチャルオフィスの特徴
京都バーチャルオフィスの強みは以下のとおりです。
・サービス内容に応じて選べる4つのプラン
・京都御所から徒歩1分の好立地
・月額2,000円〜!エリア最安値に挑戦中
・電話番号取得・転送サービス付きでも月額6,500円〜
・商談スペースもあり
特に月額料金の安さには自信があります。もし低コストで開業したい、初期費用を抑えたいとお悩みなら、ぜひ弊社にご相談下さい。
【他社よりも格安でサービスを提供できる理由】
バーチャルオフィスの多くはレンタルオフィスも併設しています。レンタルオフィスとは、デスクや会議室も提供するサービスです。この場合には広い敷地・面積を有する物件が必要になります。また受付や清掃のスタッフも雇用する必要もありますね。しかし当社はデスク・会議室のサービスを排除し、私書箱機能・住所貸し・電話 転送・Fax利用に限定し、発生する経費を削減し、業界最安値を実現いたしました。もちろん来客時の商談スペースは設けておりますのでご安心ください
京都バーチャルオフィスを利用したお客様の声
実際に京都バーチャルオフィスをご利用いただいているお客様の声をご紹介します。以下のお客様は大阪からご利用頂いています。
【ご利用プラン】ビジネスプラン
“ビジネスのアイデアはあったのですが、儲かるまでは事務所はいらなかったので、とりあえずは自宅でスタートしました。自宅やカフェなどでパソコンで仕事してますが、固定電話からの転送で会社っぽくなり助かってます。”(J.I様 男性)
京都バーチャルオフィスのプラン内容
京都バーチャルオフィスでは、以下4つのプランをご用意しています。それぞれの料金とサービス内容は次のとおりです。
| プラン名 | 料金/月額 | 主なサービス |
| エコノミー | 2,000円 |
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便受け取りなし ・ポストへ社名表示なし |
| スタンダード | 3,500円 |
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の転送 |
| ビジネス | 6,500円 |
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の転送 ・電話番号取得・転送 ・スマホから市外局番通知可能 |
| プラチナ | 11,000円 |
・名刺やHPに住所記載 ・住所の法人登記 ・郵便物の転送 ・電話番号取得・転送 ・スマホから市外局番通知可能 ・FAX利用・転送 ・商談スペース (月10時間まで無料) ・フリーダイヤル利用 |
このように、プランごとに料金やサービス内容が異なりますので、ご希望に合ったプランをお選び頂けます。どのプランが適切か悩んだ際は一度ご相談下さい。京都バーチャルオフィスでは、適切なプランをご提案し、皆様のビジネスをサポートいたします。

京都市内に所在地を置くバーチャルオフィスには東京や大阪など他府県にあるバーチャルオフィスにはない大きな特徴があります。これは京都市内特有の独自の風習から来ているものであると言えるでしょう。京都のバーチャルオフィスは、バーチャルオフィスを使っていることがバレにくいのです。その理由とは
京都バーチャルオフィス
あなたへオススメの関連記事
この記事を読んだ方には下記ページもよく読まれています

バーチャルオフィスを利用するにあたって、「郵便物の扱いはどうなる?」と気になる方は多くいるはずです。ここでは、バーチャルオフィスの特徴や私書箱サービスとの違い、郵便物の転送費用や、受取不可の郵便物等に関して解説します。

起業したばかりで、あまり人脈もない場合、取引先をゼロから開拓していかなくてはなりません。それは税理士など士業の先生を探す場合も同じです。かといって全く知らない方に依頼するのも少し不安です。そんなときに様々な会社や士業を紹介してくれるのがバーチャルオフィスです。

起業をするにあたり、自宅以外の住所が必要な時に活用したいのがバーチャルオフィスです。レンタル住所・貸し住所のサービスはもちろん、他にも様々なサービスを提供しています。しかし、名前は聞いたことがあっても、どんなサービスを受けられるのかわからないために、利用に踏み切れない方も多いですよね。

バーチャルオフィスをうまく活用すると、起業や事業運営に必要な経費を抑えつつ、事業者に必要な信用が獲得できます。「バーチャルオフィスに興味があるけど、本当に使っても大丈夫なのかな…」と二の足を踏んでいる人のために、本記事では、バーチャルオフィスの概要から利点、注意点まで解説します。

これから起業したいと考えている方のなかには、「成功するかどうか不安」「どのように成功に導けばよいか分からない」と困っている方もいるのではないでしょうか。この記事では、起業の成功率を上げるためのポイントを解説します。

バーチャルオフィスは登記が可能など便利なサービスの一方、デメリットもいくつかあります。この記事では、バーチャルオフィスの基本的なサービスに加えて、メリットやデメリット、利用前に確認しておくべきポイントや向いている人、よくある質問について解説しています。